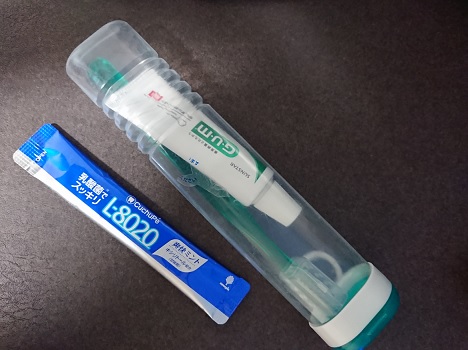「危険を感じたら非常用持ち出し袋を持って避難所または避難場所へ避難しろ」というのは、災害対策で出てくる基本的な部分の一つです。
避難場所は文字通り「避難するための場所」なので一時的に避難ができることが条件になっており、学校の校庭や公共施設の駐車場など、露天の場所が指定されていることも多いです。
では避難所はどうでしょうか。避難所は災害後に家が壊れたり何らかの事情で住めなくなった人が一時的に生活空間を作る場所であり、地域の支援物資の集積所であり、情報や人の集積所にもなっていますが、今回は「避難所で生活するとしたら?」を考えてみて欲しいということを取り上げてみたいと思います。
まず最初に、あなたはあなたが避難する避難所のことをどれくらい知っていますか。どのようなものが準備されていて、誰が運営して、どのような支援が受けられるのかを知っていますか。
この質問をして全てにきちんと答えられる状態であれば、可否はともかくその避難所のことを理解できていると言ってもいいでしょう。
一般的には、田舎の小さな集落ほど避難所として使える施設は日常の生活空間に近くなり、都会で人口の多いところに行けば行くほど過酷な避難環境になると考えて間違いありません。
田舎で避難所に指定されるのは、たいがい集会所や公民館で、こういったところは畳部屋や給湯施設がきちんと整備されていて、座布団や毛布などもあり、とりあえずはそのまま寝っ転がってもなんとか生活できる資材があることが多いです。

この間仕切りさえない避難所がほとんど。
でも、例えば避難所が学校という場合には、支援物資は何一つ備蓄されて折らず場所貸し状態というところが結構ありますから、雨露をしのぐだけの場所と考えての準備が必要となりそうです。
つまり、避難すべき避難所の状態によって自分で準備すべき身の回りのものが変わってくるということです。座布団や毛布がある畳敷きの部屋なら、寝具関係はなくてもなんとかなりそうです。でも、タイル張りの床に座るスペースしか無いとうことであれば、敷物や断熱材を用意しておかないと床の冷えを拾ってしまったり、堅い床に寝ることで身体を痛めたりすることになります。つまり設備のある避難所に避難するのであればその部分の準備は簡単にしておけばよさそうですし、設備がない避難所であれば、自分の身を守るためのさまざまな装備も持っておかないといけないということが理解できると思います。避難所に電源がなければ自分でそれも確保しておかないといけませんし、食事や飲料水などは当然準備が必要です。
避難所の状態を確認して非常用持ち出し袋の準備を整えておくと、いざというときに困ることが少なくなると思います。
とりあえず、自分が避難しようと思っている避難所に一度歩いて移動してみて、避難所ができたらどんな状態になるのかについて確認をしておいてくださいね。