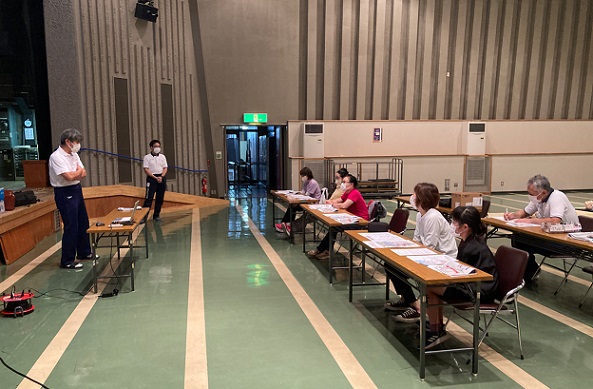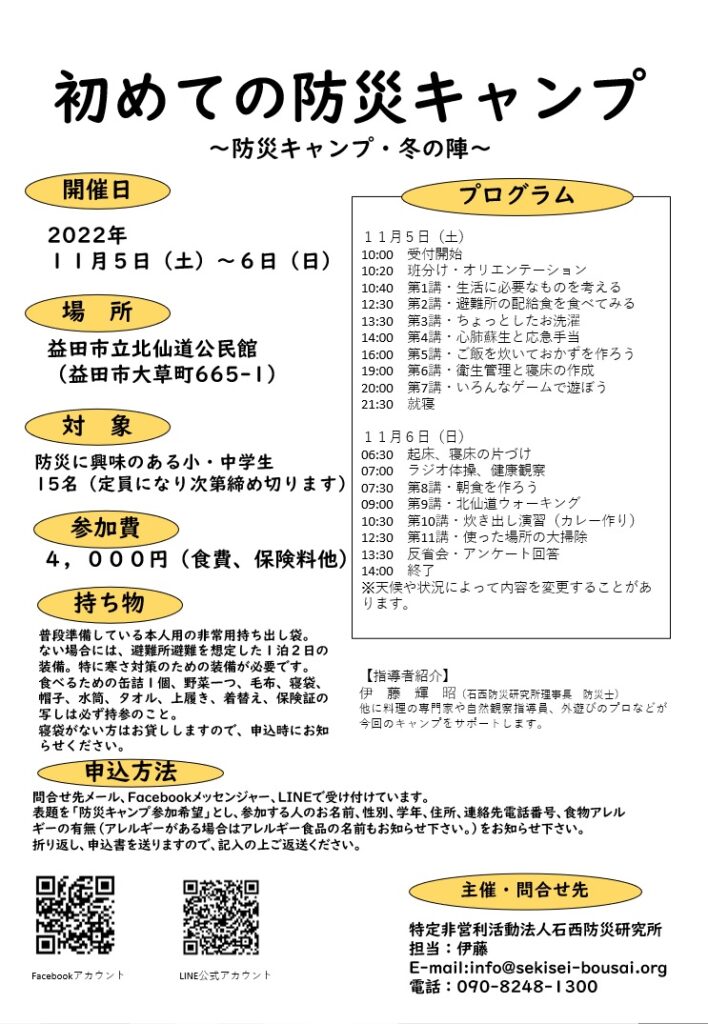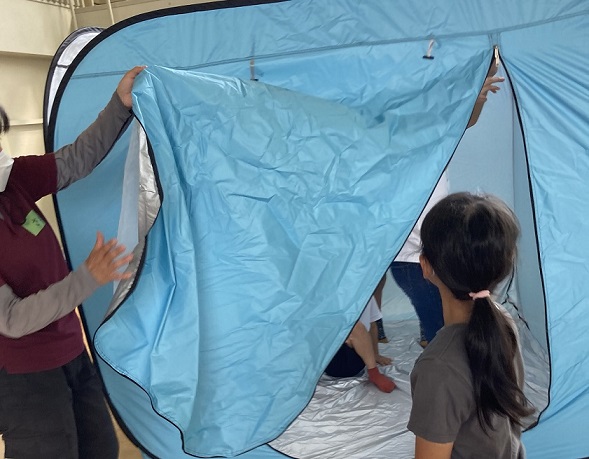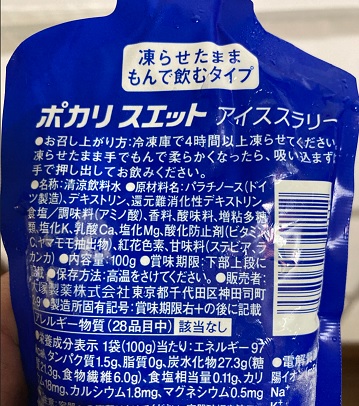去る8月7日、高津川支流の匹見川上流部で、今年度の「水難事故防止講習会&水遊び」を開催しました。
今年度は大規模周知をかける直前で新型コロナウイルス感染症の流行が始まってしまったため、主に事前周知できた当研究所研究員達の参加となってしまいましたが、水への浮き方や救助の待ち方の確認をし、川の危険な場所について目視や実際にその場所に行って水の深さや川の流れを確認していました。
 流されたら「浮いて待つ」ことが大事。
流されたら「浮いて待つ」ことが大事。
ただ、講習に入る前に投棄された釣り針を研究員が発見して確保。こういった投棄された釣り針も危険だねという話もすることができました。
 釣り針の不法投棄は危険な事故につながる。
釣り針の不法投棄は危険な事故につながる。
そのあとは恒例の水遊び。川にいるゴリを網で取ったり川流れ、沢登り、淵への飛び込みなどを思い切り楽しみ、暑い中ではありましたが、楽しい時間を過ごすことができました。
 沢の中を歩いたり、流されたり。全身の感覚を研ぎ澄ませて登っていく。
沢の中を歩いたり、流されたり。全身の感覚を研ぎ澄ませて登っていく。
途中昼食休憩のときにゴリの入った虫かごを置いておいたら、盗まれるといったハプニングもあり、今回は事故防止だけでなく防犯対策についても考えることのできる会となりました。
 毎年恒例の豚汁は今年も大好評。スイカの差し入れもいただき、川の水で冷やしたスイカも堪能しました。
毎年恒例の豚汁は今年も大好評。スイカの差し入れもいただき、川の水で冷やしたスイカも堪能しました。
日程の都合上、本年度はこれで終了となりましたが、また来年、今度は一般の親子ふれあいも兼ねてにぎやかにできたらいいなと思っています。
今回参加してくれた研究員と子供たちに感謝すると同時に、水の事故が少しでも減るといいなと思っています。