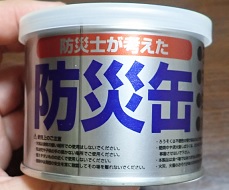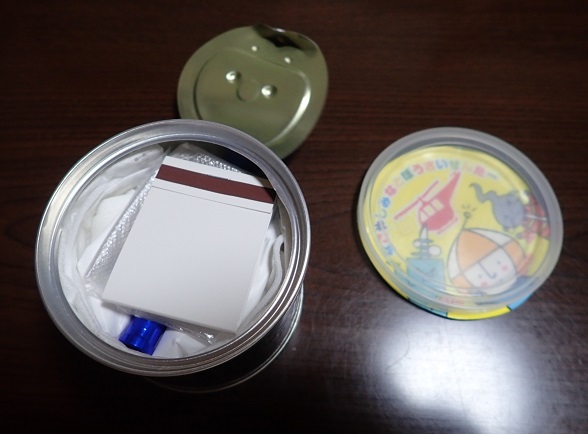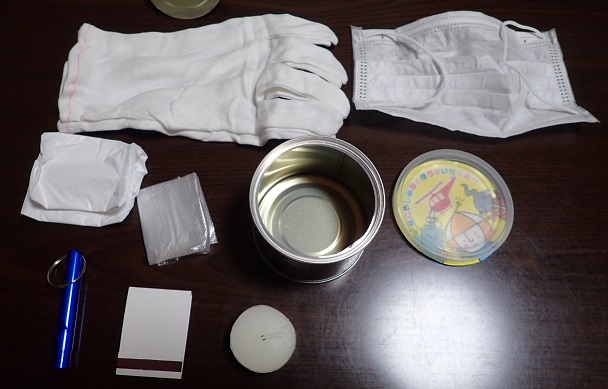災害時、主に地震のときには、よっぽど意識して片付けている家で無い限りさまざまなものが床に散乱してしまいます。特に眠っていたときなどは、揺れが収まって寝ぼけ半分で避難や片付けを行うことになりますが、そのときに自分の足を守るためのものが準備できていますか。
散乱しているものの中には、ガラスやプラスチック片など、足を切ったり刺さったりしてしまう危険なものが多くあります。そんなところを素足で歩くと、せっかく無事に地震をやり過ごせたのにしなくてもいい怪我をすることになってしまいます。一般的には運動靴を準備しておくことが推奨されていますが、置いたりしまったりする場所に悩んでしまったりします。スリッパでも、靴下でもいいので、何か足を守るものを準備しておいてください。

新聞紙を近くに置いておけば、新聞紙スリッパを作ることもできるでしょうし、タオルや服を巻き付けても構わないと思います。大切なのは足を怪我しないこと。素足で歩かなくてもすむ方法を考えてください。
「身を守る」とは、自分が安全な場所まで移動できて初めて完了する行動であり、無事に移動するためには、足を怪我するわけにはいきません。ないに超したことはありませんが、いざというときに備えて安全に逃げるために足を守れる方法を準備しておいてくださいね。