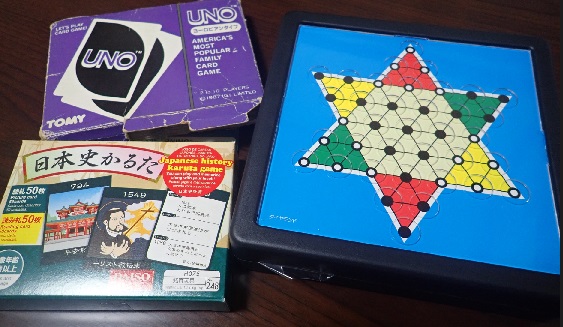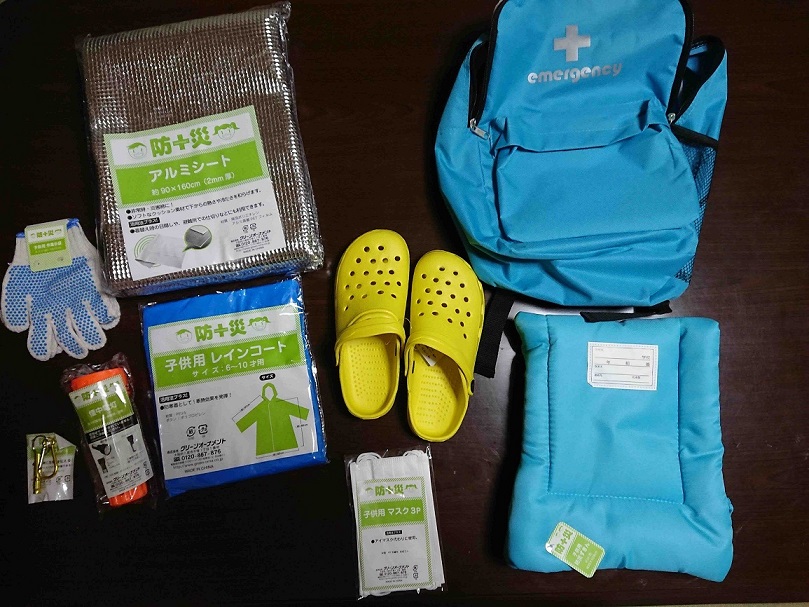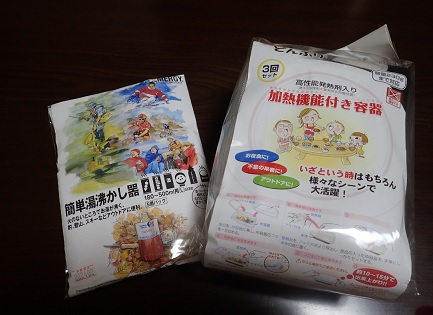今年はあまり寒さを感じさせない日が多いのですが、それでも焚き火をするにはご機嫌な季節です。そして焚き火というとやはり焼き芋は定番でしょう。
先日、とあるイベントで焚き火をし焼き芋を食べたのですが、ふとうちのペール缶コンロでも焼き芋はできるのだろうかと考え、思いついたからにはやってみるということで、いつものペール缶コンロで焼き芋作りに挑戦です。
このペール缶コンロ、普通のと違っていて底が抜いてありロケットストーブと似た構造になっていますので、少量の薪で充分暖かくなれる便利なものです。着火もしやすく、燃え残りも殆ど出ない優れもの。これに木ぎれを入れて火をつけ焼き芋を作ってみようという算段です。
着火剤として、電化製品の梱包材に使われる圧縮した紙を使ってみたら、あっという間に火が起きました。

びっくりするくらい火力があります。これに薪を加えて炭にするのですが、完全燃焼が目的のこのタイプの炉ではうまく炭になりません。
サツマイモを濡らした新聞紙でくるみ、アルミホイルに巻いて、適当なところで炉の中へ放り込み、焚き火でやるのと同じくら15分程度焼いたら取り出します。
火力調整をしていたのですが、15分経つと薪はすっかり燃え切っていました。

で、3本焼いたのですが、火力が強すぎたらしくアルミホイルが溶けてしまっているものもありました。3本中、2本はほぼ炭化。1本はなんとか食べられる状態でした。


できあがりは、それでも食べられるところはほくほくでとっても甘いものができていました。このタイプの炉で焼き芋を作るためには、普通の焚き火よりも手を加えないといけない感じです。
どんな風にしたらいいのかはこの次までの課題にしておくことにしましたが、ともあれじっくりと焼いた芋はこの時期最高のごちそうです。
安全に注意して、焚き火のできる場所で是非試してみてください。