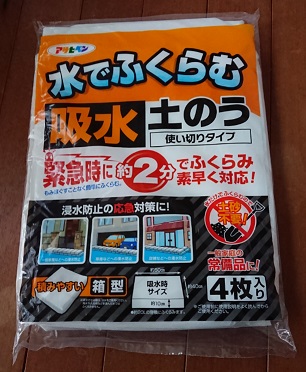大雨や台風での避難では、なるべく濡れないように早めの避難をするようにしてください。
もしどうしても大雨や水の中を濡れてでも避難をしなければならなくなったときには、しっかりと防水対策をした袋などにタオルと着替えセットを入れて、必ず持って避難することをお勧めします。
濡れたままでいると風邪を引くとはよく言われることですが、災害時でもそれは全く変わりません。
服でも靴でも、濡れるとその部分の体温は濡れている部分の水に奪われていき、たとえ夏であっても低体温症になる確率が跳ね上がるからです。
人間は身体が冷えてくると、体温を保つために熱を作ろうとします。寒いときに身体が震えるのはこのためなのですが、そのときに同時にエネルギーもかなり消費することになります。
空気に比べると、水の熱伝導率は約25倍だそうですから、いくら熱を作っても濡れている部分に熱を持って行かれて、身体がどんどん冷えてくるという事態になります。
暑い時期に海や川やプールで遊ぶと涼しくなるのは、水が身体から熱を奪っていってくれているからで、長い時間浸かっていると寒くなって水中にいられなくなると言った体験をしたことがある人も多いのではないかと思います。
災害時、避難所に身体を温める熱源があればいいのですが、冬ならともかく、夏にそんな熱源を用意してくれている避難先はまずないでしょう。
そうすると、一番確実なのは避難が完了したらすぐに乾いた服に着替えるということです。
空気は水とは逆に高い断熱性を持っていますから、着替えることで冷えた身体を温めることができます。
もちろん、濡れたままでは避難所に入れてもらうこともできませんから、着替えは必須になるわけです。
避難の時、足下は運動靴を履くように書かれている文献が多いですが、その際に替えの乾いた履き物も一緒に準備しておくと、着替え後もあなたの自由を確保することが可能です。
一番良いのは、濡れてしまう事態になる前の安全な時期に避難することです。
そのことを前提にして、それでも濡れて避難することを考え、あなたの装備の準備をするようにしてくださいね。