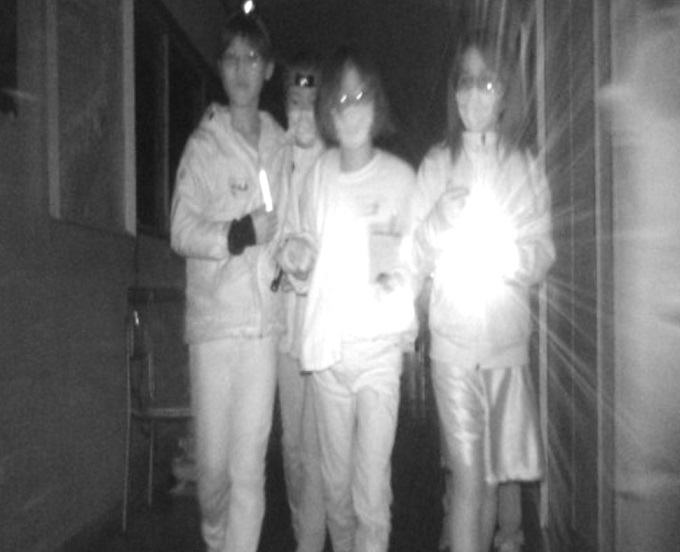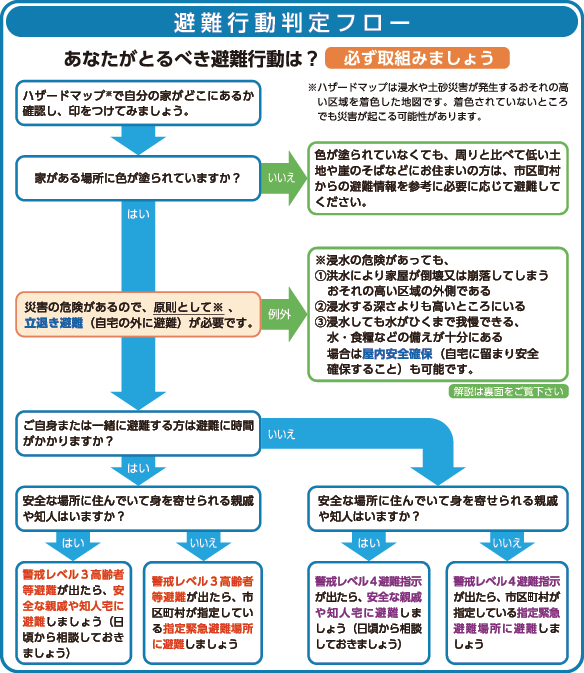何らかの理由で避難所生活をしなければならなくなった場合、いろいろと困ることが起きてきますが、その中でも他人の目については対策を講じておく必要があります。
普段の生活では、例えば家にいたり、自分の部屋に入ったりすれば他人の視線を防ぐことができるのですが、避難所ではそういうわけにいきません。
24時間常に人目にさらされる生活を送ることになりますので、それが嫌な場合にはしっかりとした対策を用意しておきましょう。
具体的には、安いものでいいので自立型のテントを一張準備しておきましょう。それがあるのとないのでは、自分の中の安心感がまったく異なります。
テントがあれば、最悪避難所以外でも安全な場所があれば、そこで張って生活する場を作ることができます。
行政が避難所に届けてくれる目隠し用の壁は、数が少ない上に視線を遮るのには中途半端な高さであまりあてにはなりませんので、当座の安全な場所として、自立型テントを非常用持ち出し袋に入れておくことをお勧めします。