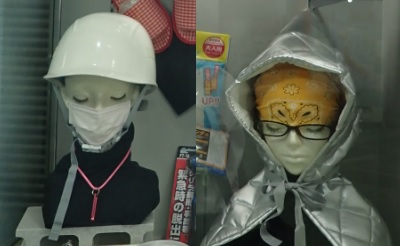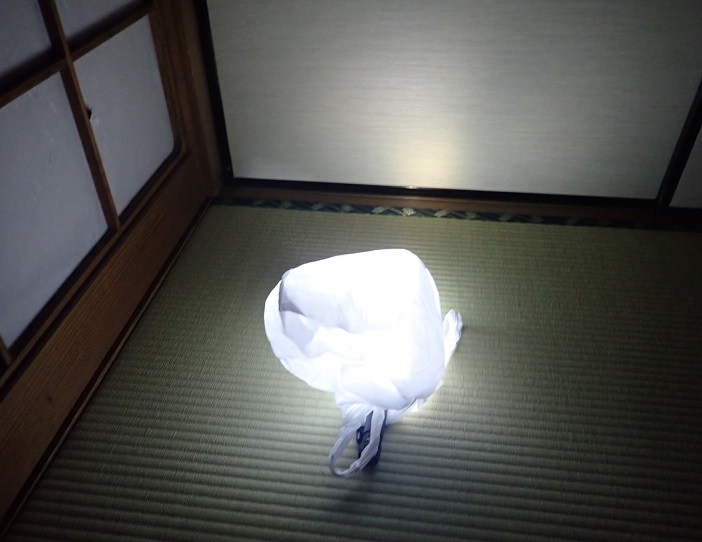新型コロナウイルスの流行は避難所の設営や運営方針についても多くの影響を与えています。
それまで割とあいまいだった避難所への避難か自宅待機かについて、基本は自宅待機、その災害で危険な場所になっている場合には避難所へ避難と明確に指示がされるようになりました。
そして、詰められるだけ詰め込んでいた避難所は、ソーシャルディスタンスを確保するために家族ごとに十分なスペースが与えられることになり、避難所の生活環境も一気に改善されることになりました。ただ、そのぶん避難所の収容人員が減らされてしまいましたので、避難所として使える施設を増やす他にも車中泊やテント泊なども避難所の一つとしてカウントされるようになってきています。
今まで避難所では避難者を受け入れることが重視されすぎていて、衛生環境の維持についてはおざなりにされていました。
そのため被災地に設置された避難所ではインフルエンザやノロウイルスといった感染性の病気が一度発生すると蔓延することがよく起きていましたが、新型コロナウイルスの流行のおかげで、避難所に感染症患者の隔離場所が作られることになり、衛生環境が改善されてきています。世界保健機関(WHO)が推奨している難民キャンプの基準であるスフィア基準にようやく追いついてきたといった感じでしょうか。
トイレの問題についてはまだまだ検討する余地があるとは思いますが、それでも災害が起きるたびに改善や改良がされてきており、悪くなってはいないでしょう。
ただ、新型コロナウイルスの影響で避難所の設営や運営方法も以前と比べてずいぶんと変更が加えられていますが、それに対応した訓練や資機材の準備が追いついていません。また、新しい避難先の周知についても避難すべき住民がまだまだ理解できていないということもあります。
新型コロナウイルス騒動がいつごろ収まるのかがわかりませんが、避難所運営に関して言えば、治まったから以前のすし詰めに戻すのでは無く、このまま新型コロナウイルス対策がなされた基準で設置して欲しいなと思っています。
余談ですが、内閣府防災が新型コロナウイルス対策で避難所運営についてのポイントを整理した動画を作成しています。
興味のある方はご覧いただき、参考にしていただければと思います。
新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイントについて(内閣府防災情報のページへ移動します)