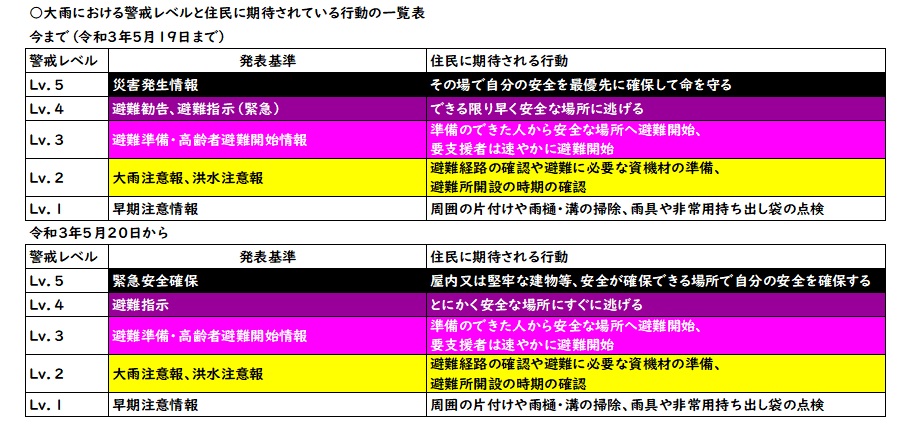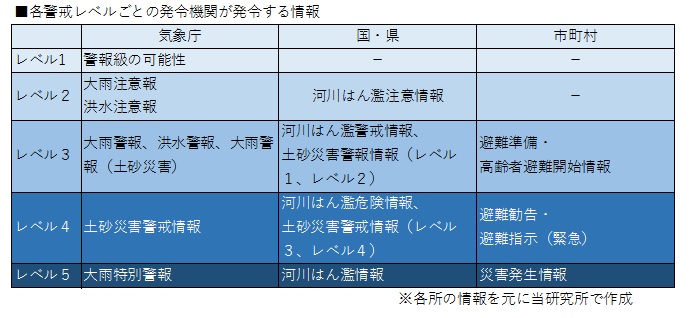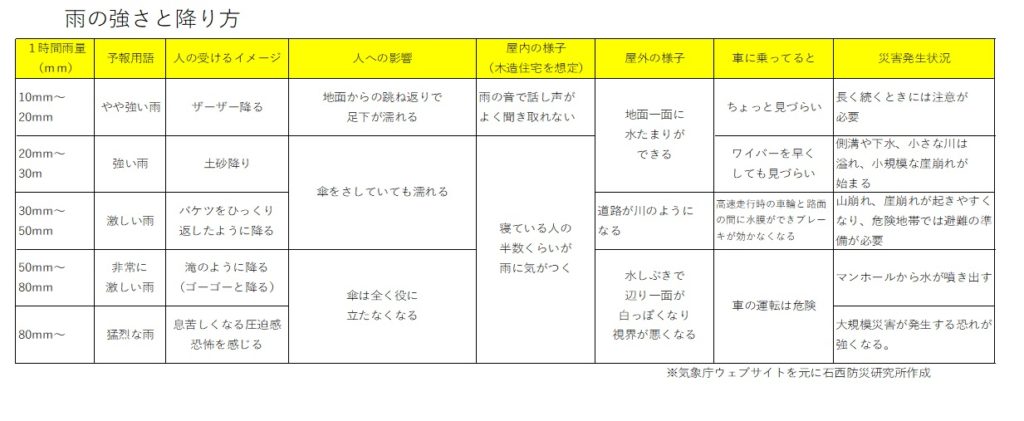避難訓練の支援をさせていただいていると、「他人事」になっているなと感じる人達が殆ど全ての場所で確認できます。
「かっこ悪いことはしない」という感じで、なぜ訓練をしなければいけないのかを理解いただけていないのかなとも考えますが、他人事になると退屈ですので見物状態やおしゃべりに夢中になってしまい、訓練参加者がシラケてしまうという事態が発生します。他人事になっているのは殆ど100%避難する人ではなく、避難誘導すべき立場の方なのを考えると、本当にこれで大丈夫なのだろうかと不安になります。
避難訓練をやることが目的になってしまっていて、やる前、やっているとき、やった後の検証作業もせず、かなり適当に実施して終わったことにするような場合もあり、これならいっそやらない方がいいのかもしれないなと思うようなものもあります。
もっとも、防災担当がいるような会社や組織は殆どなく、たまたま仕事のついでに防災担当をつけられたような人が片手間にやるのであれば、毎回同じマニュアルで訓練をすることも仕方がないのかなと思います。同じ内容であれば、毎回参加する側は考えなくてもいいので非常に楽ですし、参加者の評判もいいわけですから。
ただ、本番ではマニュアル通りにできることはまずありません。状況を無視してマニュアル通りにしようとするとどうなるのかは、「想定外」という言葉を考えてもらえばわかるのではないでしょうか。
訓練では、失敗が起きることが大切です。その失敗の解消方法を検討して実行することで、より本番に近い訓練ができ、結果的に本番でも命を守ることができるのではないかと思います。
また、避難訓練の参加者それぞれが、自分の命をどうやって守るのかを考えながら行う避難訓練であれば、いざ本番でも確実に自分の命を守るべき行動をとることができるようになっていきます。
せっかく訓練をするのですから、しっかりと考えて避難訓練が本番で生かせるようにしておきたいですね。