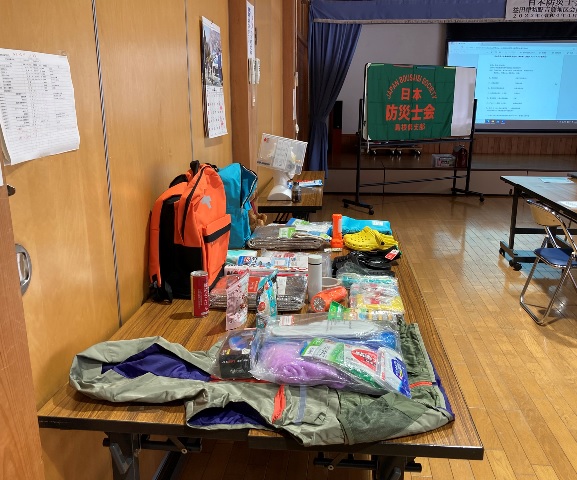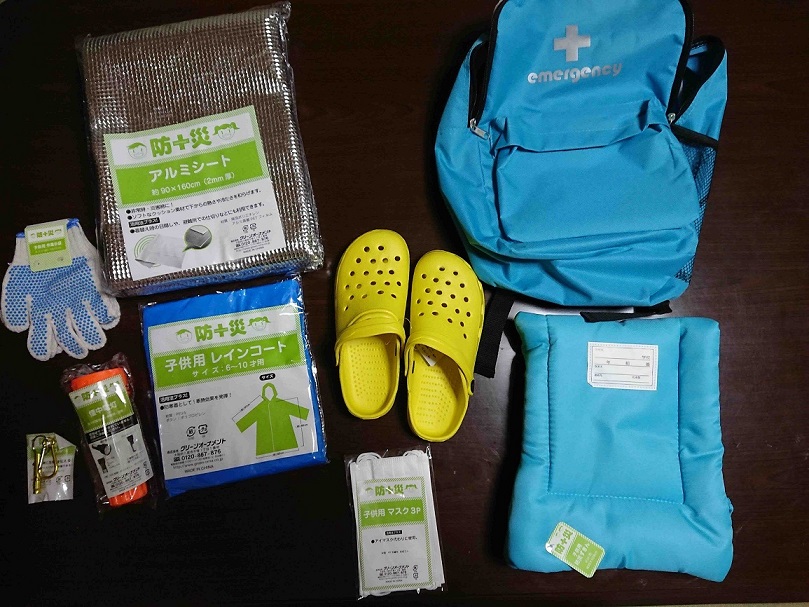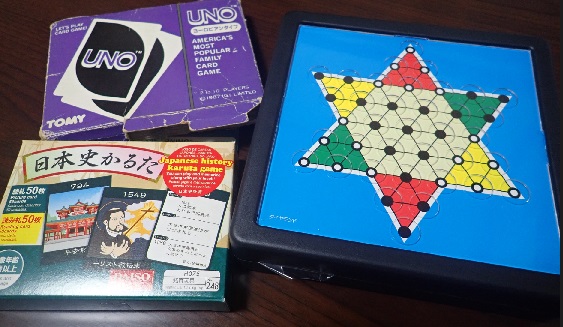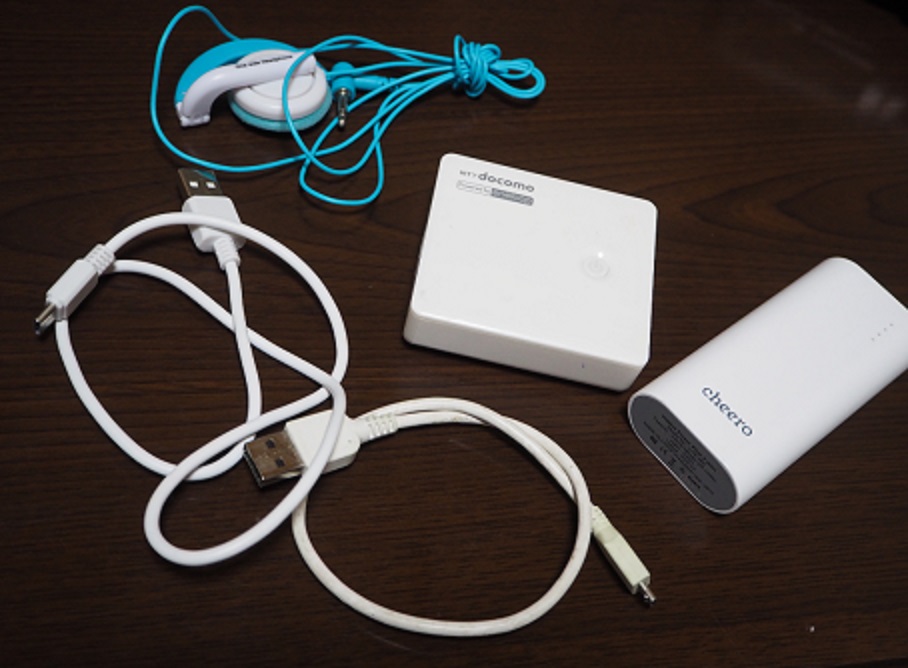大雨が降るかもしれないという予報が出ていますが、あなたの家の周りの側溝はきれいになっていますか。
側溝は排水路ですので、水をせき止めるものが中にない限りは降った雨を川などに運んでくれるありがたいものです。
ただ、注意が二つ。
一つは側溝の中が汚泥やゴミなどで底が埋まっていたり、水がうまく流れなくなっていないかを雨が降る前に確認しておくこと。
二つ目は、あなたの家の周りの側溝が、周囲と比べて低地になっていないかどうかということです。
水がうまく流れるためには側溝にゴミがあったり、汚泥などで浅くなっていたら困るのはわかると思います。
低地の問題は、側溝の排水能力を超える雨が降ると、低地部分から水があふれ出してしまうからです。
もしも家の周囲がその低地に当たるのであれば、周囲に土のうを積んでおいたり、あるいは雨の様子を見て早めに安全な場所への移動を開始したりといった方策を考えておく必要があります。
当たり前のことですが、水は高いところから低いところへ流れていきます。
周囲から低い場所にあなたの家や避難経路があるのであれば、他の人よりも行動を早くしたほうが安心です。