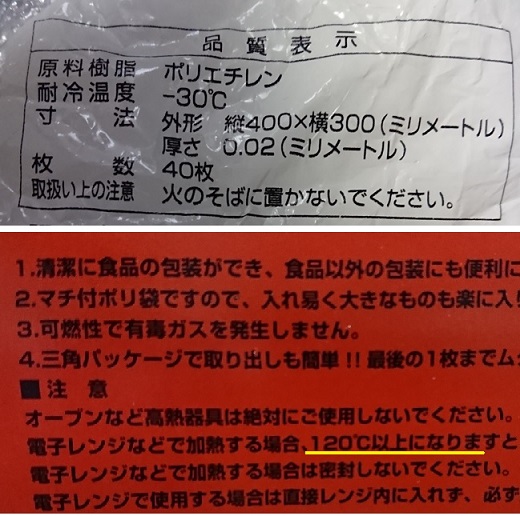災害が起きると、断水や停電、浄化槽や下水道管の破損などでトイレが使えなくなるケースが結構多いです。
トイレが使えない状態なのに無理やり使うと、トイレの中は大惨事になってしまいますので、できるならトイレがちゃんと使えることが確認できるまでは使用を禁止するようにしてください。
そうなると必要になってくるのが仮設トイレや携帯トイレ。
ただ、個人や自治会、自主防災組織などで準備はしていても、これを組み立てたり使ったりすることはほとんどないのではないでしょうか。
普段使っていないものは、いざというときにも使えませんので、防災訓練のときには実際に使ってみてください。
また、避難所で設営が必要な仮設トイレは、訓練のたびに出して組み立て、使いかたをしっかりと確認しておくことはとても大切です。
トイレは我慢ができません。そのあたりに穴を掘ってすることにしてしまうと、周囲の衛生状態に深刻な問題が発生します。
災害時のトイレ設営は最優先されることの一つなのです。
いざというときに慌てなくて済むように、携帯トイレの準備、そして実際に使ってみること。
仮設トイレは実際に組み立てて、これも使ってみること。
この部分の訓練は手を抜かないようにしたいですね。