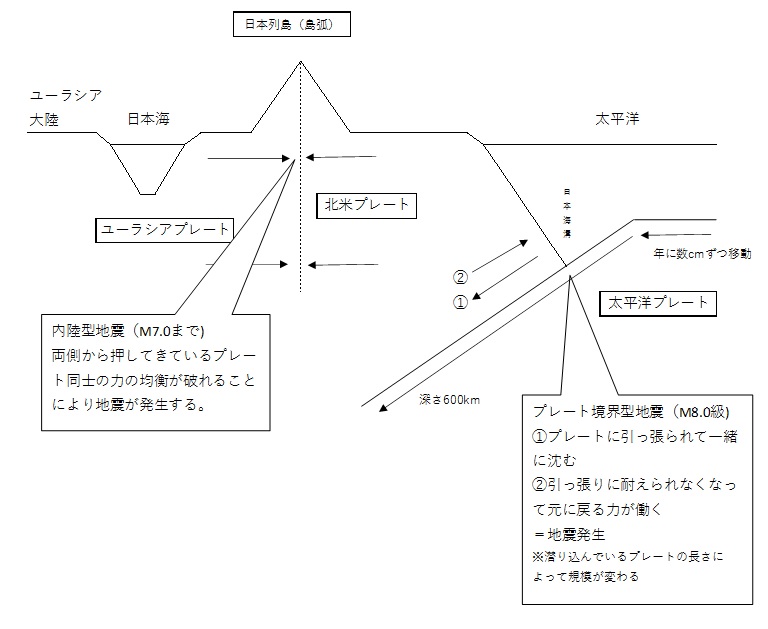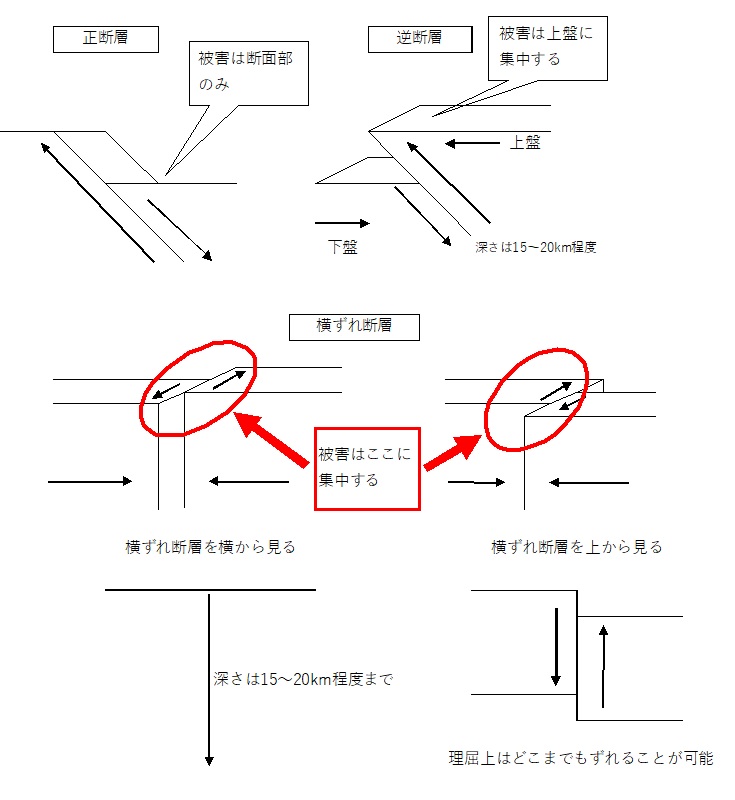地震が起きると、電力会社は被災した一帯の送電を止めます。
発災後、電柱や電気施設の確認をした上で通電を再開するわけですが、この時、地震で壊れた電化製品や断線した電気コードがショートしたり、電気ストーブなどの暖房器具が倒れてきた洗濯物や本など可燃物と接触したりして火災が起きることがあります。
これを通電火災と呼びますが、1995年の阪神淡路大震災で起きた出火はこの通電火災が原因とされているものが数多くあります。
また、東日本大震災でも、発生した火災の6割が通電によるものとされ、中には避難所として使われていた施設も、通電火災により閉鎖になったケースもあります。
電力会社でも対応は進めていて、2016年4月の熊本地震では通電火災は0件となっています。
これは通電前に通電予定箇所を広報して回ったり、倒壊した家屋への引き込み線を撤去することにより達成できたものです。
とはいえ、規模が大きくなったり被災範囲が広範囲になってしまった場合には、全ての場所に電力会社が対応できるとは限りません。
そのため、自衛手段として配電盤を「感震ブレーカー付き」にしておきましょう。
感震ブレーカーと言ってもさまざまな種類があり、配電盤内に感震装置を内蔵しているものや設定した揺れが起きた段階でボールやバネの力によりにブレーカーのスイッチを切るするものなど、いろいろあります。
GV-SB1 リンテック21 感震ブレーカーアダプター【簡易タイプ】 YAMORI(ヤモリ) |
簡易型感震ブレーカー「スイッチ断ボール3」 SWB03 |
感震ブレーカーはその名の通り地震に対して有効な電源切断装置ですが、他の災害では機能しません。
そして、地震以外の災害時でもブレーカーで電気を遮断しなくてはいけないことは変わりません。
ただ、いきなり来る地震ではブレーカーによる電気遮断のことを忘れがち。
そのため、自分の財産を守るためにも、周囲を燃やさないためにも、感震ブレーカーを設置するようにしましょう。
また、当たり前ですが普段から電気ストーブやファンヒーターの周りには可燃物を置かない、使っていない電化製品はプラグを抜いておくといったことも意識しておくようにします。
東京消防庁の調査では、東京消防庁管内で発生したストーブ火災のうち、電気ストーブによるものが実に7割を占めていたそうです。
災害時だけでなく、普段からも火災を出さないように意識したいものですね。