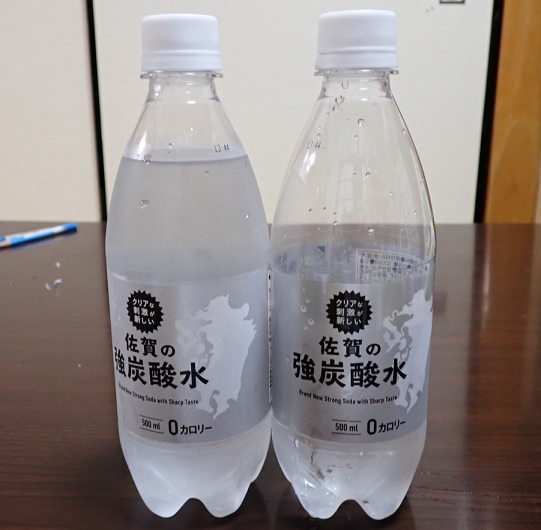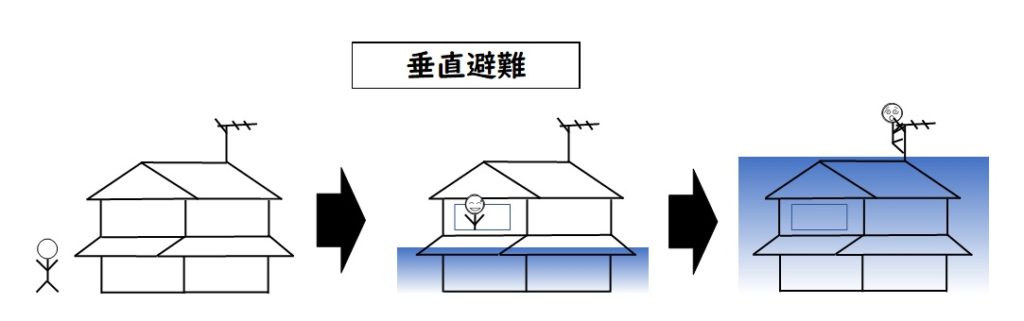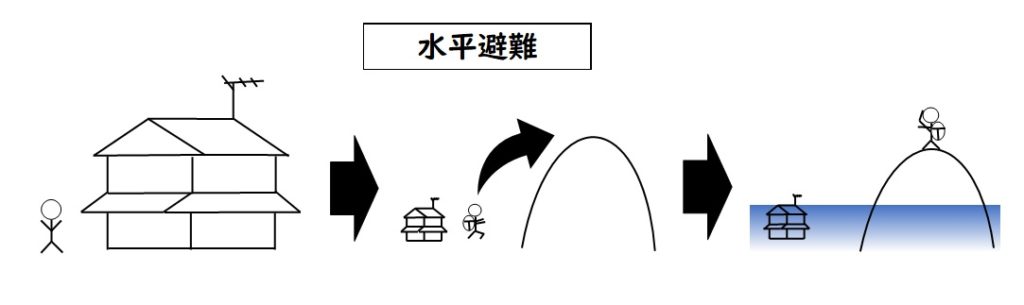ラジオを聞いていたら、恐怖体験として「山でこぐまに出会ったので必死に逃げた」という話をしていました。
パーソナリティーの方は「子供でもくまですからね。小さいけど」といった感じだったのですが、それを聞いていて、クマの生息域に住んでいる人やそういうところを登山する人ならこの話の本当の怖さがわかるのになと感じ、わからないというのはこういうことなのかと妙に納得しました。
「子グマがいる」というのは、別に子グマが脅威なわけではありません。いえ、子グマでもよほど小さな個体でない限りは人間よりも力が強くて十分脅威なのですが、それ以上に怖いのが、その子グマのすぐ近くに母グマがいて、状況によっては問答無用で襲われるということなのです。
たぶん、山に登る人も同じような印象を持つのではないかと思いますが、子グマは無警戒にいきなり現れます。そして、理不尽なのですが母グマは人を見ると子グマに対する脅威と見なしてかなり警戒していて、ちょっとでも母グマが子グマが危険だと感じたら、即座に攻撃をしかけてきます。
話をしていた人はそのことを前提にしていたと思うのですが、子グマには気を荒くしている母グマがついているということを知らなければ、単に「かわいい小さなクマがどうして怖いんだろう?」という印象になってしまうのでしょう。特に動物園ののんびりしたクマしか知らない人もいるわけで、そうなると怖いということが理解できないのかもしれません。
人が危険を感じるためにはそのことが危険であるということを知っておかないといけないのだなと、今回の話でちょっと考えさせられました。
危険を知ること、できれば危険な目にあってみること。
人が的確な判断をするためには、そういった経験が重要なのかもしれません。