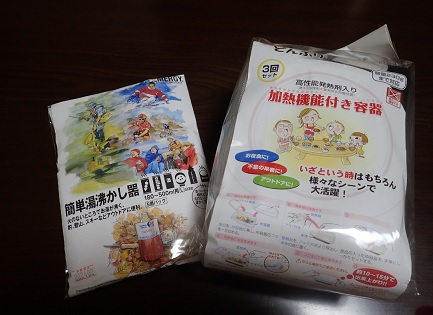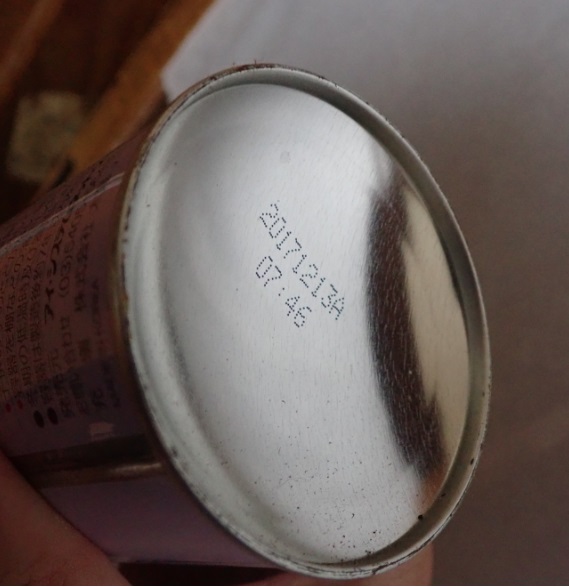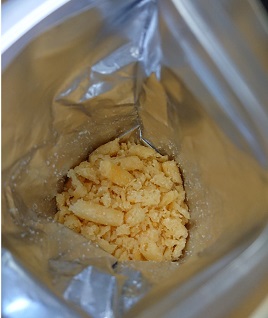今日は七草がゆの日。おせち料理を食べて疲れてしまった胃腸を整え、野菜が乏しい冬場の栄養を補うという理にかなった風習です。
もっとも、現代では普通に野菜が売られていて食べることができますので、昔ほど栄養を補うという要素は重要視されないのかなとも思います。
さて、この七草、「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」の七種類で構成されていますが、野草としては冬でもしっかりと生えているものばかり。つまり、災害が起きたときに食料となり得るものなのです。
元々野菜は食べられる野草を品種改良して食べやすくしてきたものなので、味はともかく、野草も食べることはできます。ただ、生えている草を片っ端から摘んできても、中には食べられなかったり処理が必要だったりするものもありますから、食べるためにはその処理方法や調理法も知っておく必要があります。
地域によって食べられる野草が生えている場所や生えているものが異なりますので、お住まいの地域でどのようなものが生えているのか、どうやったらおいしく食べることができるのかについて、余裕のあるときに調べて食べてみるといいと思います。
春の七草は、そういう意味では日本国内であればわりと手に入りやすい野草たちですから、それらの野草から探してみてもいいかもしれません。
被災後に生き残るためには、食べられるもの食べられないものを判別できる能力が不可欠です。調べて食べてみて、自分の口にあうものを見つけておけば、いざというときでも焦らなくてすむかもしれませんよ。