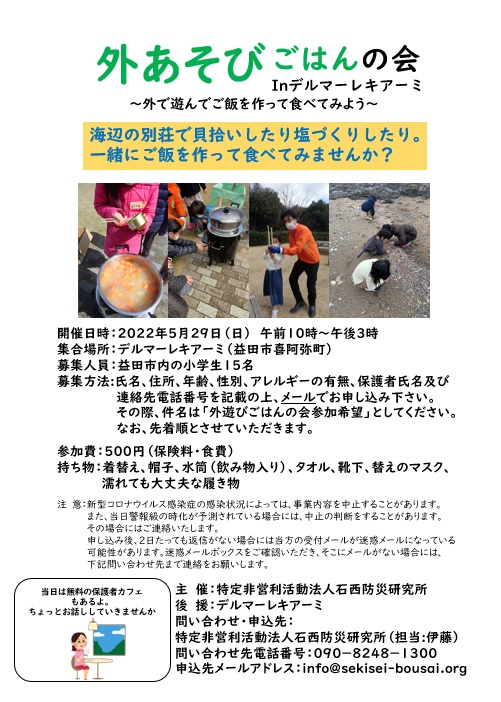年末年始にかけて地元の山間部でも雪が積もりましたので、状況偵察を兼ねて広島県の深入山に出かけてみました。
コロナ禍が落ち着いてきたせいか去年よりも雪遊びをしている人達は少なかったですが、いくつかの家族がそり遊びを楽しんでいました。
雪山というと寒くて危険というイメージがありますが、装備と段取りさえ間違わなければしっかりと遊ぶことができます。
普段と違った景色が見られて面白いものですが、行き慣れている里山でも装備が整っていない状態では危険なので、今日はどこでもできる冬の雪遊びを少し紹介してみたいと思います。
1.足跡観察

雪の上には、さまざまな野生動物の足跡が残されています。
都会地の公園や路地裏でも、雪が積もっていると何かの生き物の足跡を見つけることができるものです。
足跡を探し、それがどのような生き物なのかを当てっこするのはとても面白いですよ。
うまくいけば、足跡の主に出会うことができるかもしれません。
足跡探しに夢中になると迷ってしまうこともあるので気をつけなくてはいけませんが、一度はやってみてもいいと思います。
2.ヤドリギ観察
野鳥の多い地域では木にヤドリギがついていることがありますが、普段は葉で見ることが出来ません。
でも、冬場は葉が落ちていますので、木についているヤドリギをはっきりと見ることができます。
運が良ければ、ヤドリギの実も落ちているかもしれません。
この実はとても甘いのですが、非常に粘っこいので、種を口から出すときに糸を引いたりすることがあります。
このねばねばで木にへばりついてヤドリギになるのだなということがわかるくらいねばねばしてますので、一度は食べてみてもいいと思います。
食べるときには、あくまでも自己責任でお願いします。
3.そり遊び

意外に思われるかもしれませんが、そりは少しの雪でも滑って遊ぶことができます。
地面が露出しているところではさすがに無理ですが、全体が白くなっていればその上で滑って遊ぶことは可能です。
滑りやすい傾斜地を見つけることと、滑り降りた後に安全が確保されていること。
この二点に気をつけて遊んでみると、とても面白いです。
ちなみに、全体が白くなる程度の雪で大人が滑ろうとしても、大人の重さで雪がつぶれて滑ることができません。
どこまでなら誰が滑ることができるのか、その境を探すのも面白いと思います。
4.雪だるまづくり

雪だるまは雪が少量でも多くてもそれなりに作ることができます。
積もっている雪でどこまで大きなものを作ることができるのかをやってみるのも面白いのではないでしょうか。
雪だるまを競争で作ると雪の取り合いになることがあるので、複数の雪だるまを作るときには、雪を集める場所をそれぞれ決めておくといいかもしれません。
少人数でも遊べるような雪遊びを少しだけご紹介してみましたが、イメージが沸くでしょうか。当研究所の冬の自然体験企画もこれらを組み合わせてやっていたりしますので、活動報告や写真を見られたときにこんなことしたのかなと思いながらみていただけるとうれしいです。
最後に、冬の雪遊びでは濡れると身体を冷やして風邪を引いてしまいますので、遊ぶときには防水・防風のしっかりした、例えばスキーウェアなどを着て、足下を長靴など水の入らない履き物で遊ぶことをお勧めします。
街の中と自然の中では遊ぶ格好が少し異なるので、そこだけ気をつけて楽しんでいただけると幸いです。