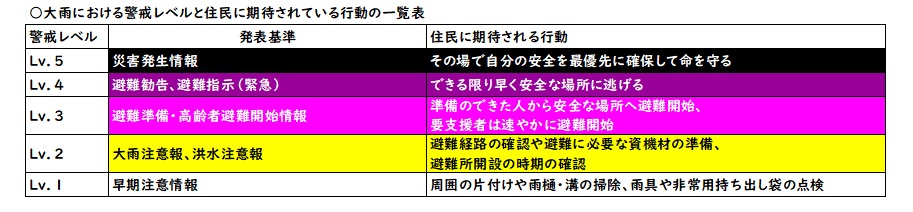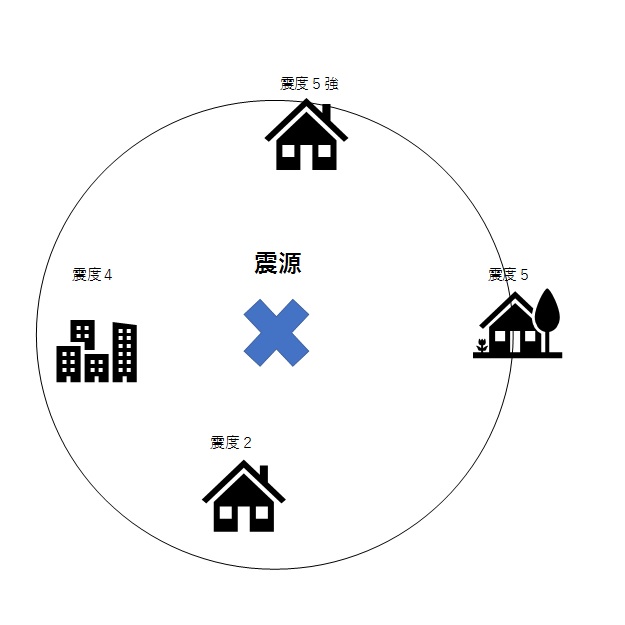2016年のときの雪景色。
2016年のときの雪景色。
年末年始は大きな寒波が来るそうです。
夜の間に雪が一気に降り積もってしまうこともありそうですので、予め積雪対策はしておいたほうがいいかもしれませんね。
新型コロナウイルスの移動自粛ではありませんが、大雪のときにも不要不急の外出は控えて天気が落ち着くのを待つというのは基本です。
でも、何らかの事情で道路を車で走らなければいけないことが起こりうるかもしれません。
そんな方は、出かける前に以下の点に注意しておいてください。
1.車のタイヤはしっかりとしたスタッドレスタイヤになっているか。
四輪駆動車などをお使いの方の中には「四駆だから大丈夫」と不思議なことをいう人が一定数いらっしゃいますが、二駆であれ四駆であれ、道路に設置しているのはタイヤです。そして、普通のタイヤは雪道を走るようには設計されていません。
正確に書けば、「雪道を走れても止まれない」のです。
普通のタイヤだと、走り出せても止まれませんので、高確率でどこかに突っ込んでしまいます。
また、スタッドレスタイヤは普通のタイヤよりも経年劣化が早いですので、保管状況にもよりますが、3年も使うとしっかりと効かなくなってしまいます。
まだ山があるからと言って古いスタッドレスタイヤを履くのはかなり危険です。
道路で立ち往生して動けなくなる車の中には、結構高確率で古いスタッドレスタイヤを履いている車がいるそうですので、そうならないためにもきちんと使えるタイヤを履かせておきましょう。
2.タイヤチェーンは積んでいるか。
スタッドレスタイヤも圧雪状態ではなかなか効果が十分に発揮できません。
そんなとき、タイヤチェーンがあればしっかりと走ることができます。
また、雪道からの脱出時にもタイヤチェーンがあったほうが安心できます。
金属チェーン、ゴムチェーンとありますが、どちらでもいいのできちんと準備しておきましょう。また、あらかじめちゃんと巻くことができるように練習しておくことは言うまでもありません。
3.スコップは積んでいるか。
もしも動けなくなったときには雪をどけて道を切り開く、またはその場で救援を待つとして車内暖房を効かせるためにエンジンを回すとき、排気管が雪に埋もれるのを防ぐために排気管の周りを定期的にほる必要があります。
そのためには、先が平らな平スコップまたは除雪スコップを準備しておきましょう。
4.幹線道路以外は走らない
大雪になると、幹線道路以外の道路の除雪は後回しにされます。
そのため、普段使っている迂回路だからと狭い道に入ってしまうと、そこで動けなくなると救援が来るのがいつになるか分からない状態になります。
自分も困りますし、周囲にも迷惑をかけますので、幹線道路以外は走らないようにしましょう。
5.燃料はできるだけ入れておく
普段の感覚で大丈夫だと思っていても、道路で動けなくなると車のエンジンを使っての暖房が生命線になります。
そのため、大雪でどうしても出かけないといけない場合には、できるだけ燃料を満タンにして出かけるようにしましょう。
ちなみに、軽油の場合は暖地と寒冷地では仕様が異なりますので注意してください。
まだまだいろいろな注意点はあるのですが、大雪のときには車でも歩いてでもできる限り出かけないのが基本です。
どうしても出かける場合には、上記の点そして下記のリンク先の中もしっかりと確認してもらって、安全に出かけて帰ってこられるようにしてくださいね。
「雪道・アイスバーンでの運転の注意点」(JAFのウェブサイトへ移動します)