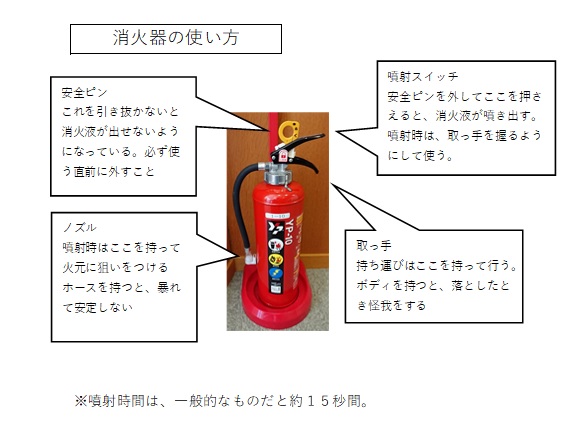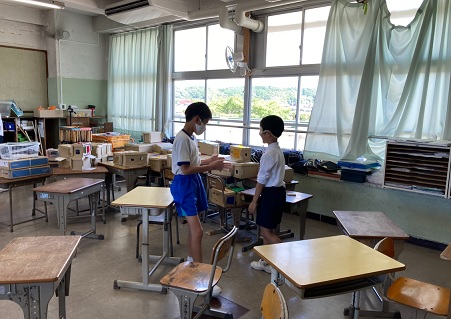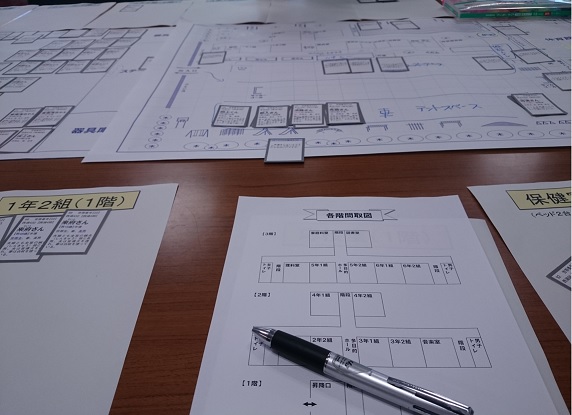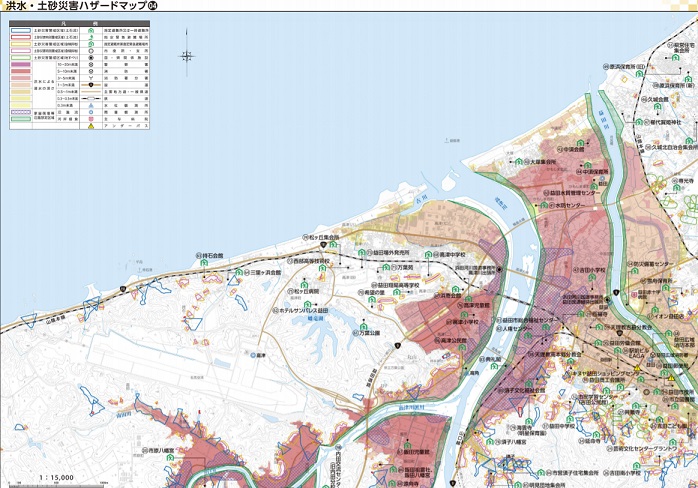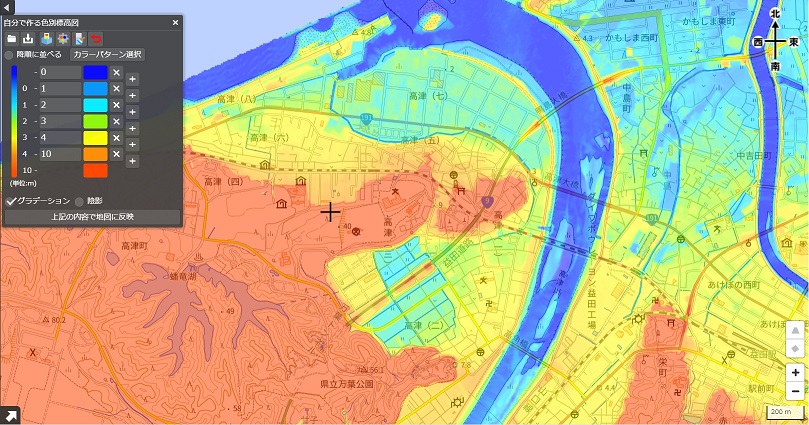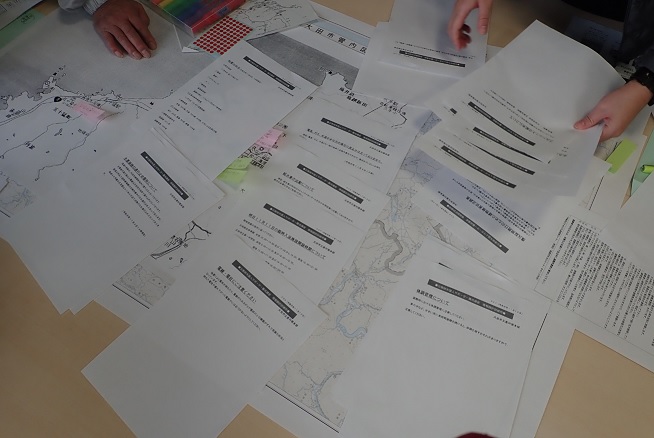ここ数日暑い日が続いていますが、ここ数年、暑くなってくると熱中症についてさまざまなところで注意が呼びかけられています。
暑いところで起きる熱中症ですが、似たようなものに熱射病や脱水などがあったりして、筆者自身はどう違うのかいまいちピンときていません。
そもそも熱中症ってなんでしょうか。
今回はざっくりと熱中症について調べてみたいと思います。
1.熱中症とは?
熱中症とは、何らかの理由で体温が上がったことにより、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能が働かなくなって体温上昇、めまい、けいれん、頭痛など、さまざまな症状の総称です。
このうち、強い直射日光によって起きるものが日射病、車や部屋の中といった閉ざされた空間が高温になって起きるものを熱射病、汗や尿など体内の水分は出て行くのに適切に水が供給されずに起こるものを脱水症状と言います。
お年寄りは感覚が鈍いため、自分が熱中症になったことに気づいたときには自分が動けない状態になっていることが多いですし、地面に近く水分の調整が未成熟な子どもも発症しやすいです。
ようするに、熱中症は「高温多湿な環境に身体が適応できなくなることにより生じるさまざまなトラブルの総称」だと考えればよさそうです。
ただ、放っておくと重度な後遺症や死亡を招く場合もあるので症状の初期でいかに適切な対応をするかがとても大切です。
2.熱中症が発生しやすい条件
1)気温が摂氏25度以上のとき
2)湿度80%以上の湿度が高いとき
3)直射日光や日差しの照り返しなど日差しが強いとき
4)無風もしくは風が弱いとき
5)暑さ指数が高いとき
これらの条件が単独だったり重なったりしたとき、体調によって熱中症が発症します。環境省が運用している熱中症警戒アラートは、この熱中症が発生しやすい条件が揃うと発令されますので参考にするといいでしょう。
3.発生する症状
1)めまいや顔のほてり
2)筋肉痛や筋肉のけいれん
3)身体のだるさや吐き気
4)異常な汗(多量または出ない)
5)体温の上昇
6)皮膚の異常
7)呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない、一時的な意識の喪失
8)腹痛
9)水分補給ができない
といった症状があったら、熱中症を疑います。新型コロナウイルス感染症のおかげであちこちに非接触型の体温計が設置されていますので、体温はこまめに確認しておくと安心です。
4.対応方法
いずれにしても涼しい場所にすぐに移動させます。クーラーの効いている部屋が一番ですが、なければ風通しのよい日影でも構いません。
可能であれば衣服を脱がして皮膚に水をかけ、うちわなどであおいで身体からの放熱を助けます。
氷や冷えた保冷剤があるなら、首筋や脇の下、太ももの付け根など、皮膚のそばを大きな血管が走っている場所を冷やして身体の冷却を助けます。
とにかく体温を下げることを目的として身体を冷やします。
身体の深部体温が摂氏40度を超えると全身痙攣などが起きて危険な状態になることがありますから、あらゆる手段を使って身体を冷やしてください。
意識がはっきりしていて飲み物が飲めるなら、冷たいスポーツドリンクや経口補水液を飲むことで、身体の内部から温度を下げることも可能です。
ただし、意識がなかったり混濁していたり、吐き気を訴えたりしているときには無理に飲ませないでください。
「3.発生する症状」の(5)~(9)の場合には救急搬送が必要となりますので、身体を冷やす作業をしながら救急車を手配してください。
5.熱中症の予防
とにかく暑さを避けることです。涼しい服装で、クーラーの効いた部屋で過ごすこと。窓を開けていても熱風が吹き込んでくることもありますので、涼しい環境を意識して作るようにしてください。
自宅が暑くてどうにもならないときには、図書館などの公的施設に出かけてみるのも手です。
また、コロナ渦で標準装備になっているマスクは口元に熱が籠もって体温上昇を招く元です。外出時のソーシャルディスタンスを確保できないときを除いて、なるべく外すようにしてください。どうしてもつけないといけない場合には、負荷のかかる運動や作業はしないようにしてください。
こまめな水分補給も大切です。喉が渇いていなくても、30分~45分程度に一回は水分をとるようにしてください。このとき、利尿作用のあるカフェインを含む飲料、例えばコーヒーやお茶は飲むと利尿作用によって脱水症状を招くこともありますので、できるだけカフェインの入っていない飲み物を取るようにしてください。
熱中症は気がついたときには一人ではどうにもならない状態になっていることもよくあります。なるべく誰か人のいるところで水分を取りながら暑さをしのぐというのが、一番よいのかもしれませんね。