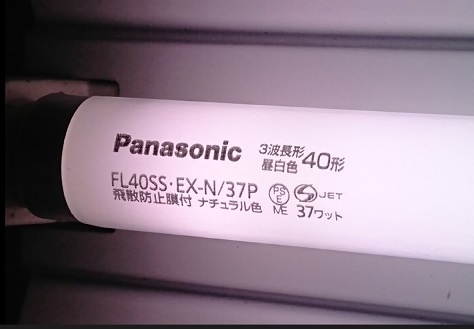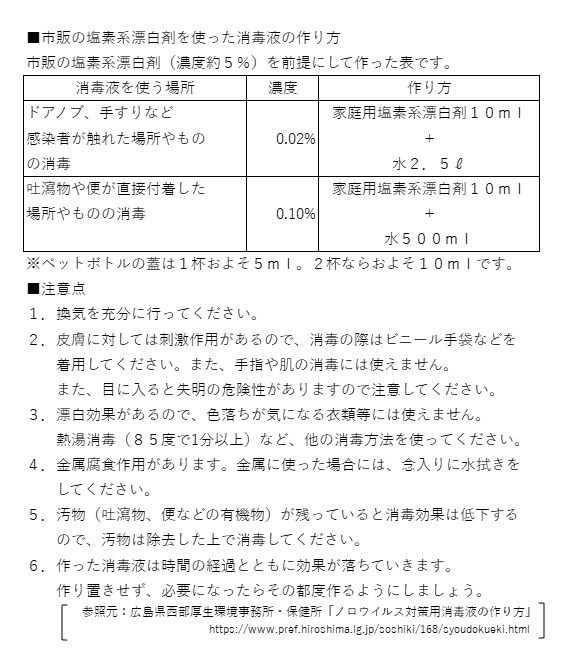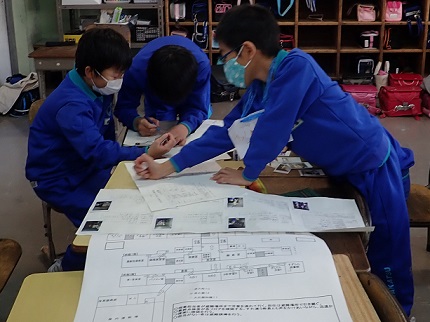防災関係で最近よく耳にするようになった言葉に、「BCP」と「タイムライン」があります。
どちらも災害に備えて作っておくものですが、中身は少し違っています。
今回はBCPとタイムラインの違いについて考えてみたいと思います。
1.BCPとは?
BCPはBusiness Continue Planの略で、日本語では事業継続化計画と言われるものです。
難しい言葉ですが、その内容をわかりやすくすると「災害前にどのように被害を防ぐか」「災害発生時にいかに被害を減らせるか」「災害後にいかに速やかに被害前の状況に戻せるか」の三つを決めておくということです。
一例をあげてみます。
まず、地震に対する被害を防ぐ方法として「タンスを固定する」行動をしたとします。
その結果、地震発生時にタンスが倒れるという被害を防ぐことができ、もしかするとタンスのある空間にいたかもしれない人も助かりました。
タンスが倒れるという被害を防げたことから、けが人を防ぐことができ、散乱したタンスの中身を迅速に部屋の中のお片付けができるようになった。
こんなイメージでいいと思います。
一つ一つ被害が起きそうな原因を特定して対策をし、その災害で受ける影響を可能な限り低減するのが目的なので、施設や人員の追加や移動などがあった場合には必ず見直しが入るものです。
2.タイムラインとは?
タイムラインとは、日本語では行動計画と言われるものです。
災害に関していえば、災害が発生したときに命を守るための行動とその行動を起こすための鍵を決めておくことです。
一例をあげてみます。
大雨で災害が起きそうな状況になっているとき、レベル3「避難準備・高齢者避難情報」が発表され、近くの高台の避難所へ避難したと考えてください。
この場合、命を守るための行動が「近くの高台の避難所へ避難する」ことで、その行動を起こすための鍵が「レベル3発表」ということになります。
タイムラインを作るときには避難情報の中にある「住民が取るべき行動」が参考になりますので、それを参考にすると作りやすいです。
一度作った後、実際に避難行動をしてみて内容を変更していきます。大きな変更はないかもしれませんが、見える場所に貼っておくなど常に意識できる状況を作っておくことが重要です。
3.BCPとタイムラインの違い
タイムラインはBCPの中の一部、「災害発生時に人的な被害をいかに減らすか」という部分だけを切り出しているものだと考えるといいと思います。
当研究所では、避難計画についてのご相談をいただくと、まずタイムラインを作るようにお勧めしています。これはタイムラインができればそれに合わせる形でBCPを作ることが可能だからです。
BCPではいかに被害を防ぐか、被害を低減させるか、そして被害前の状況に戻せるかということまで検討しないといけませんが、タイムラインはシンプルに「命を守るための行動計画」を考えればいいので、取っつきやすいと思います。
タイムラインができてから、その前後の被害の防止、物的被害の低減、被害からの復旧について決めておくとBCPも作りやすいです。
また、タイムラインは災害種別毎に作った方がいいのですが、とりあえず一つ作ってみることでどのように作ったらいいのかがわかります。そして、タイムラインは居る場所によっても異なってきますので、例えばおうちにいるときだけでなく職場や学校にいるときにはどうするかということも決めておくとよいと思います。
いかがでしょうか。BCPとタイムラインは似て異なるものですが、どちらも作っておいた方がよいものです。
施設や学校ではBCPは必ず作らなければいけないものとなっていますが、中身を見ると本当にそれができるのかと首をかしげるようなものや、「誰が決定する」としか書いておらず、その決定者が不在の場合には決められないような不完全なものが多いです。
BCPにしてもタイムラインにしても誰もが見て同じ行動ができるようにまで具体化しておかないと意味がありません。
そのことを念頭において、まずはタイムラインから作成してみてください。
なお、当研究所でも作成のお手伝いはしておりますので、何から手をつけたらいいのか悩んでいたり具体化についてうまくいかないなど、何かありましたら一度お問い合わせいただければと思います。