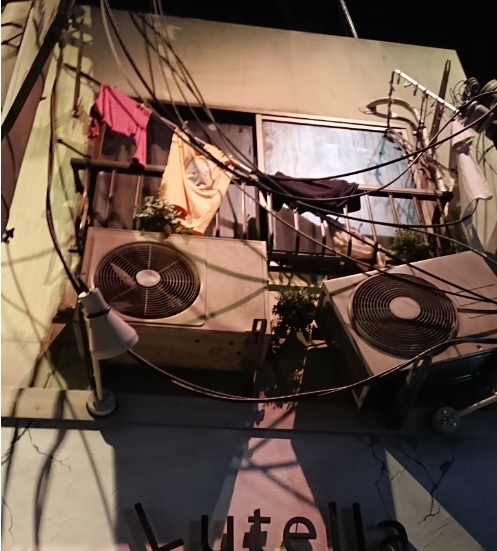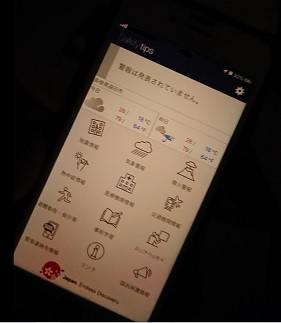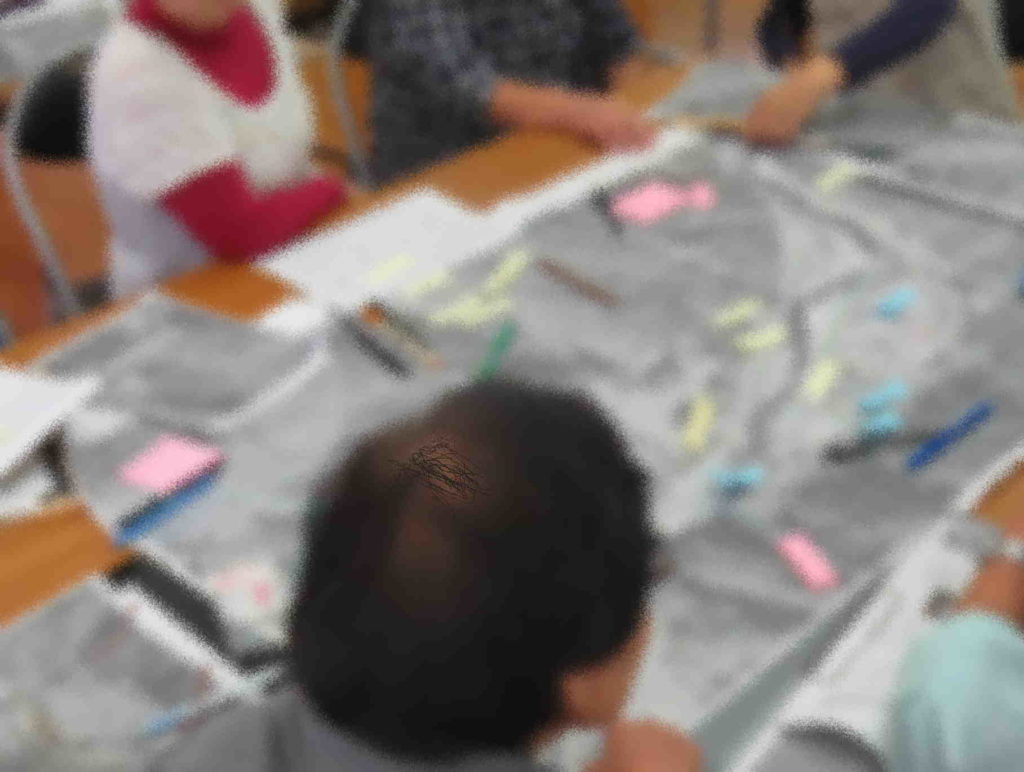
各自治体ではハザードマップを作成して自治体内の世帯に配布していますが、あなたは見たことがありますか。
ハザードマップは特定の条件下での被災状況を図化したもので、自治体や地域の避難計画作成の基礎となる資料の一つです。
これには地震や浸水害、土砂崩れの危険性が色分けで表示されていて、とりあえずの危険な場所がわかるようになっており、あなたが避難計画を作るときには必ずこれを見ているはずです。
ハザードマップの検証では、自宅からの避難だけでは不十分です。勤務先や通学先、途中の経路、よく買い物や遊びに行くところ、そして自分が避難すべき避難所の災害対応状況といったものも確認しておかなければいけません。
避難所は災害から身を守るために避難するところなので、避難すべき避難所がどのような災害に対応しているのかを正確に把握しておかなければ、避難した避難所で被災したと言うことになりまねません。
想定される災害のハザードマップに、地域の災害伝承の情報を追加すると、より安全な避難を行うことができるようになりますので、分かる範囲で確認して追加しておきましょう。
避難経路は状況や環境の変化によって常に見直しが必要ですし、地域としての防災マップ作りも必要となるでしょう。
今住んでいる場所だけでなく、自分が行きそうな場所の経路と安全性を確認しておいて、いざというときに備えたいですね。