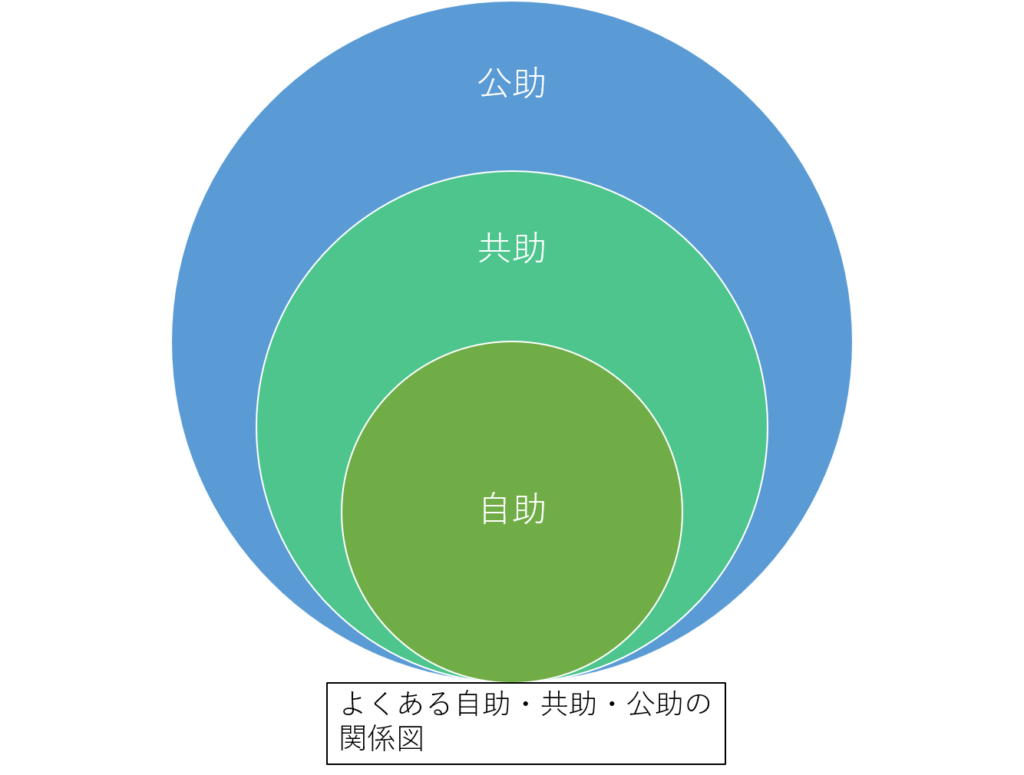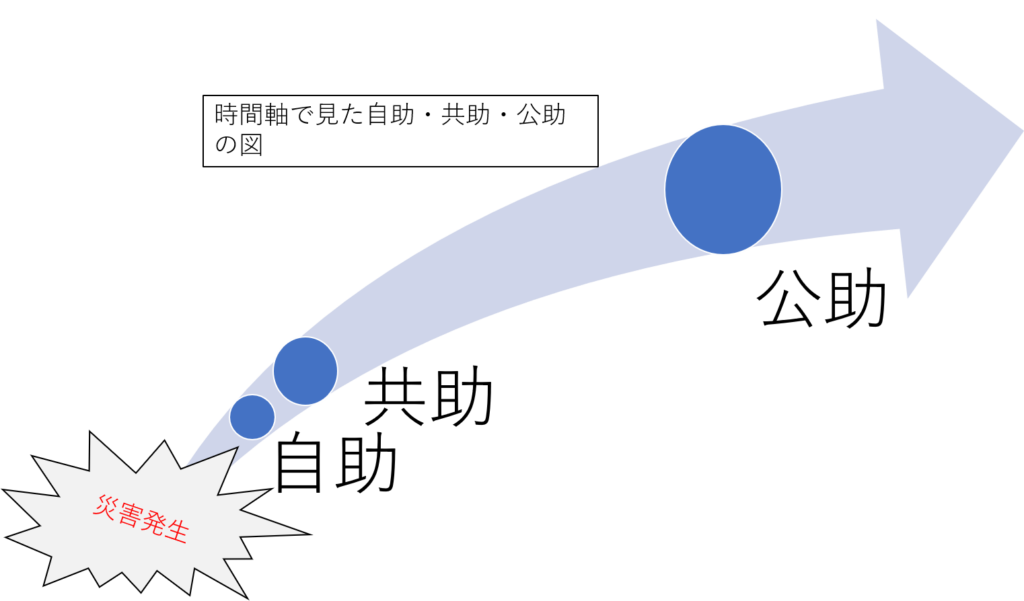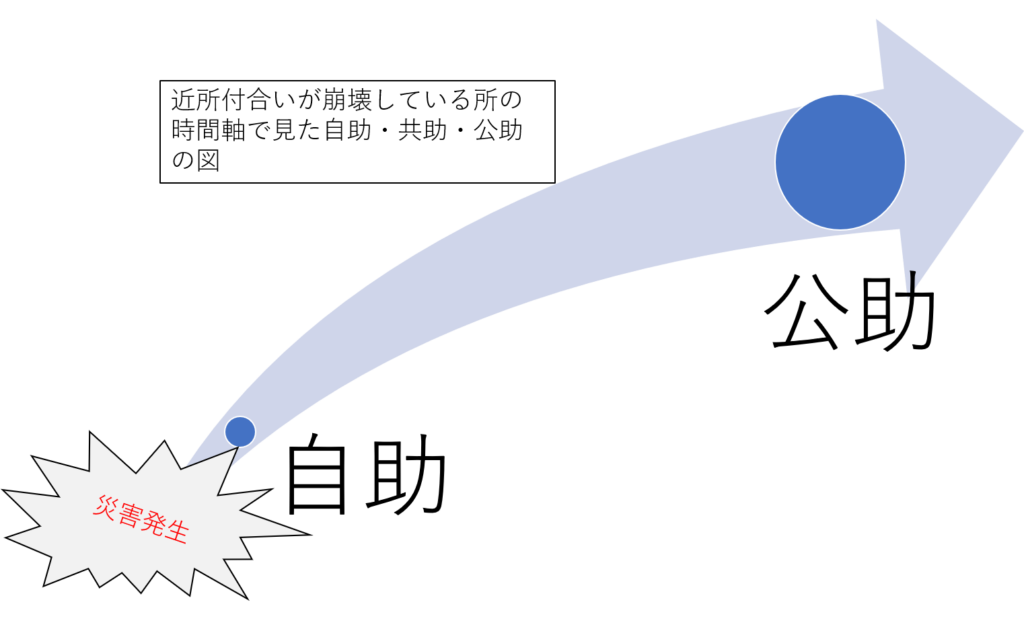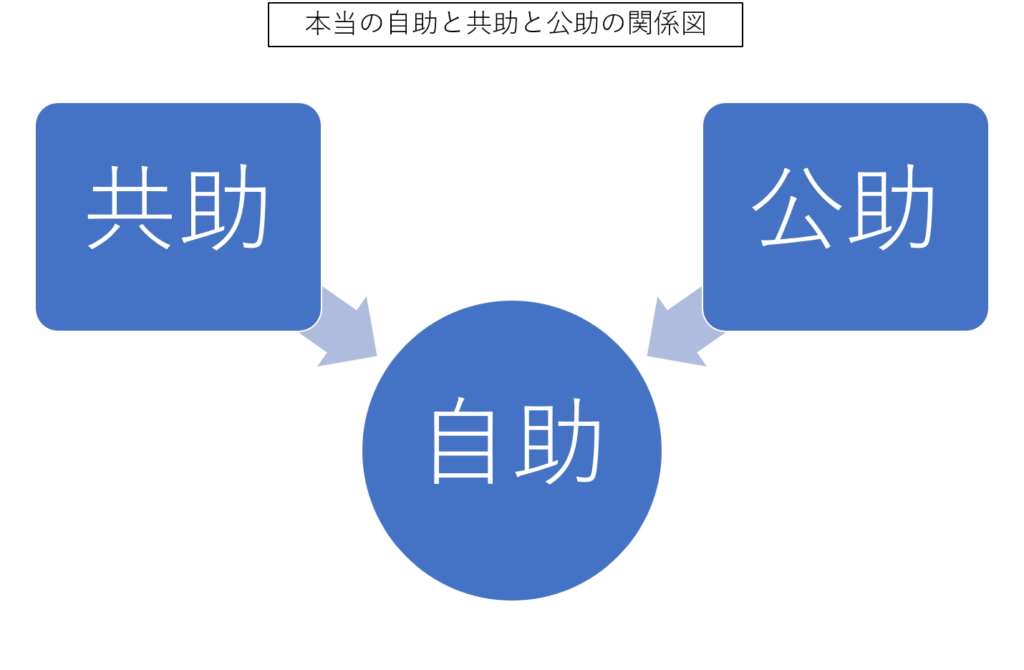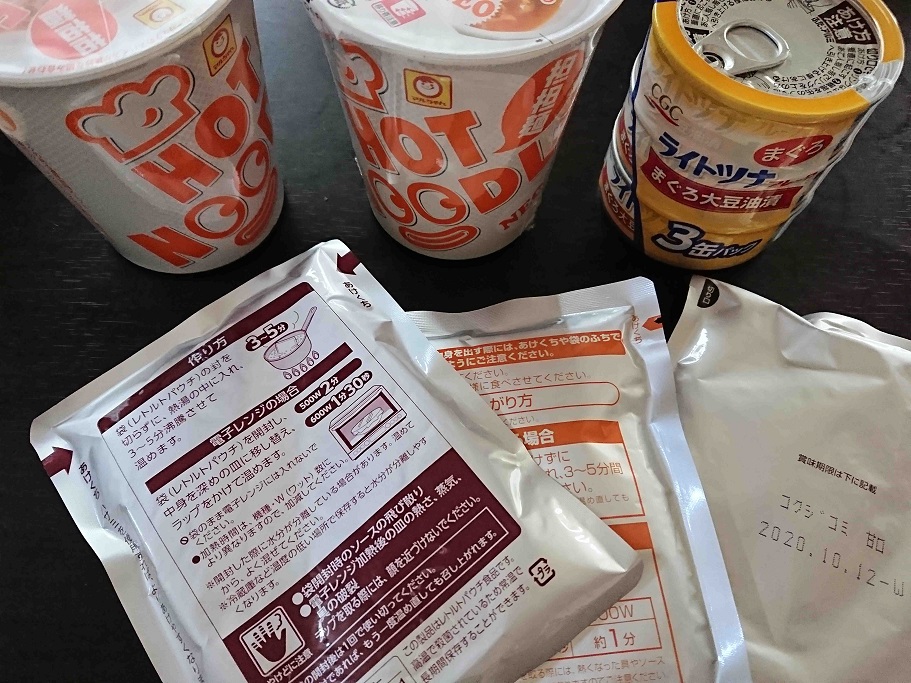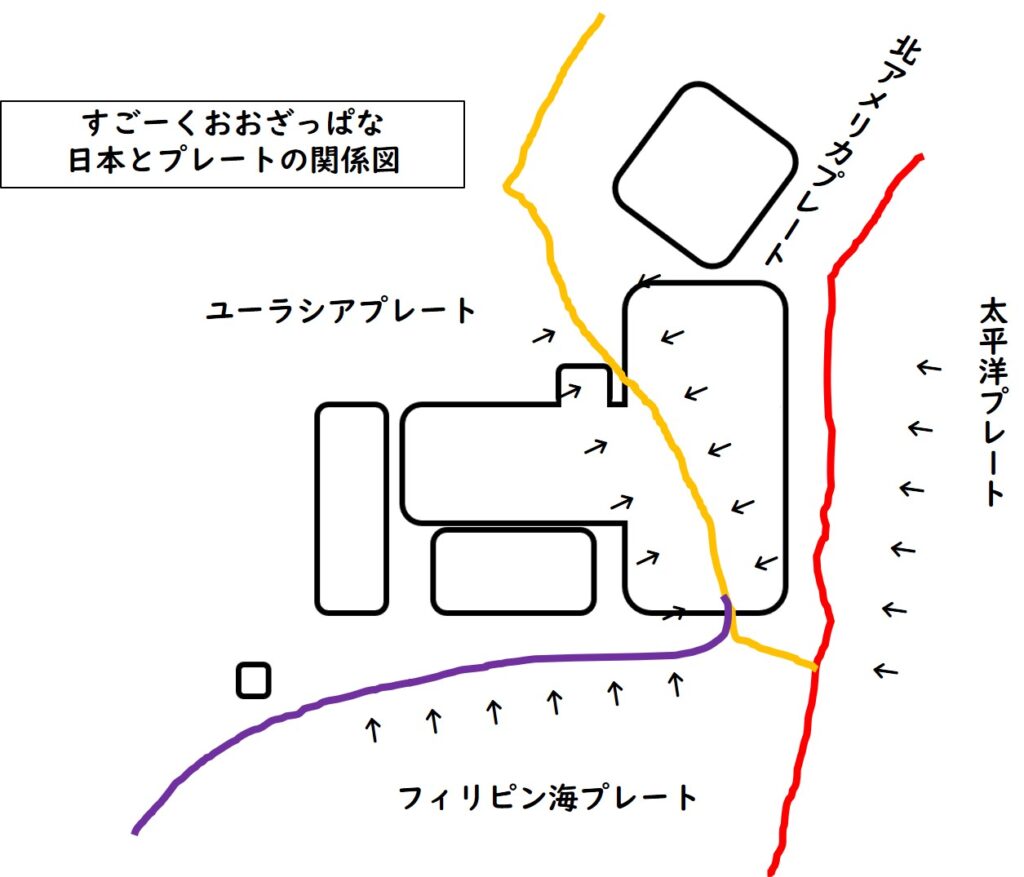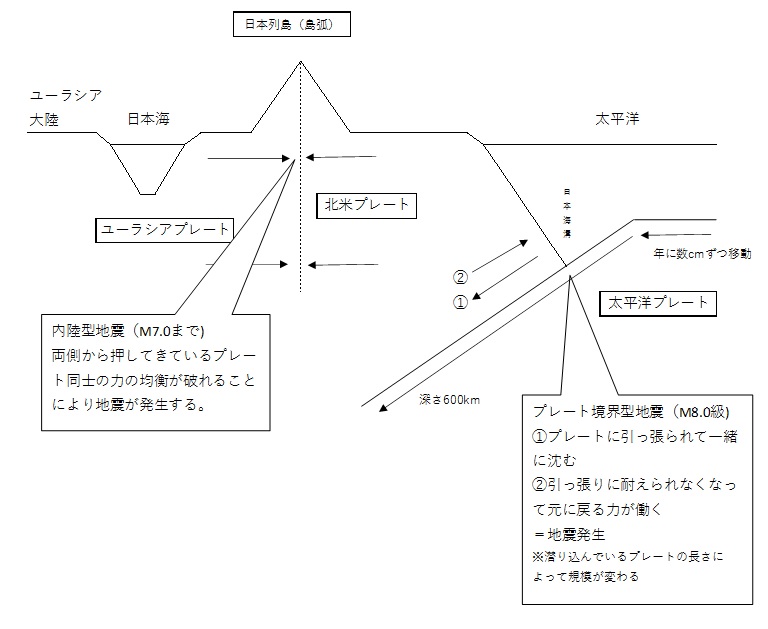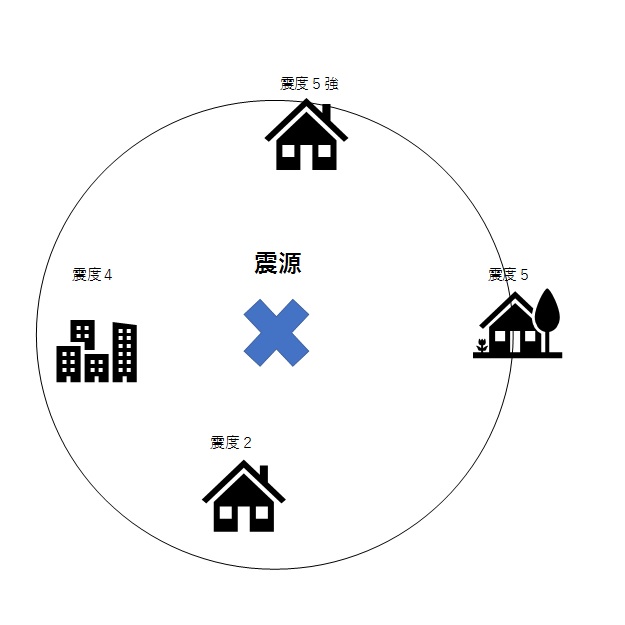災害対策、特に地震では対策をするときに一番最初に言われるのは耐震補強、または耐震化という話です。
家の倒壊を防いで命を守るということが一番の目的ですが、被災後にできるだけ避難所に避難しなくても済むことも大きな理由の一つです。
もしお手元に避難所一覧があれば確認していただきたいのですが、避難所の大きさと収容人員を比べてみてください。その避難所の建物の中に、全ての避難者が生活スペースを確保して収まるでしょうか。
多くの避難所は収容能力を超える避難者が割り当てられています。
公的な施設に全ての住民を納めるとこうなりますということなのですが、実際に災害が起きると避難者が収容しきれずにあふれ出してしまうという事態が発生しています。
では、もしも家から避難しなくて済むとしたらどうでしょうか?
家の安全が確保されているのであれば、避難時に危険な目に遭う可能性のある避難所への移動はしなくてもよくなります。
また、住み慣れた家ですからどこに何があるかも知っているし、他人の目も気にしなくて済み、ストレスも少なくて済みます。
できるだけ自宅から動かなくて済むように準備することが、災害対策のとても重要な位置をしめているのではないかと、筆者はそんな気がしているのです。
もっとも、全ての家が安全な場所に建っているわけではありません。水害や台風などで被害を受ける場所にあるおうちだってあるでしょう。
幸い、地震以外の災害では、大抵の場合何らかの前兆があります。自分の住んでいる場所がどうなったら危険なのかをあらかじめ調べておいて、どうなったら安全な避難所への避難行動を開始するのかを決めておけば、とりあえずの安全を確保することは可能になります。
あなたのお住まいの家は地震に強い作りになっていますか。
そして、他の災害で被災が予測されるような場所ではありませんか。
災害対策は、それを確認するところから始まります。