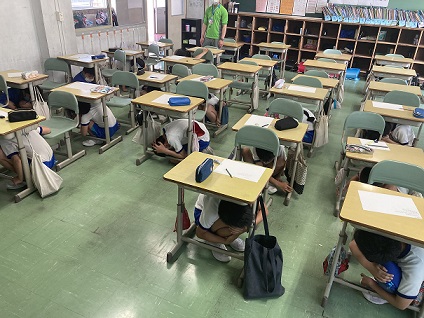さまざまな災害で被災すると、できるだけ早く日常生活を復旧する必要がありますので、可能な限り早く片付けを始めようと考えるものです。
ただ、その前にやっておいて欲しい事が一つあります。
それは、被災状況の写真をしっかりと撮っておくということです。
被災した家屋やその他被災したあらゆるものを写真に撮影しておいてください。
それも、いろいろな角度から撮っておくこと。そして、巻き尺など数値のわかるものや比較対象となるものを一緒に撮しておくことです。
これらの被災写真は、被災後に必要となる罹災証明書の作成に非常に役に立ちます。被災地域によっては、写真があれば現地調査不要で罹災証明書が発行される事もあり、いろいろな角度からの写真があれば、現地調査の代わりをしてくれるのです。
基本的に罹災証明書の発行は現地調査の後でされるのですが、人がやる都合上、どうしても時間がかかります。
そのため、必要なときに罹災証明書が手元に無いという事態も考えられます。
また、家財保険や火災保険の災害特約などを請求する場合にも、写真がしっかりと撮られていればそれだけで手続きが開始できる場合があり、迅速な保険金の支払いにも繋げることができます。
近くや遠くや角度を変えてなど、写真を撮る手間はありますが、最近ではデジタルなので場所も現像代もかかりませんから、こんなものまでといった感じの写真まで撮っておくといいと思います。
被災したときの写真は、あなたの復旧の手助けをしてくれます。可能な限りたくさんの写真を撮って、それから復旧作業にかかるようにしてくださいね。
余談ですが、罹災証明書の申請手続きや保険請求の手続きは難しくありません。書類の作成については、行政や保険会社に確認すればきちんと教えてくれます。
せっかくの保険金や見舞金が奪われてしまうこともありますので、間違っても飛び込みの代行業者などに任せないようにしてください。