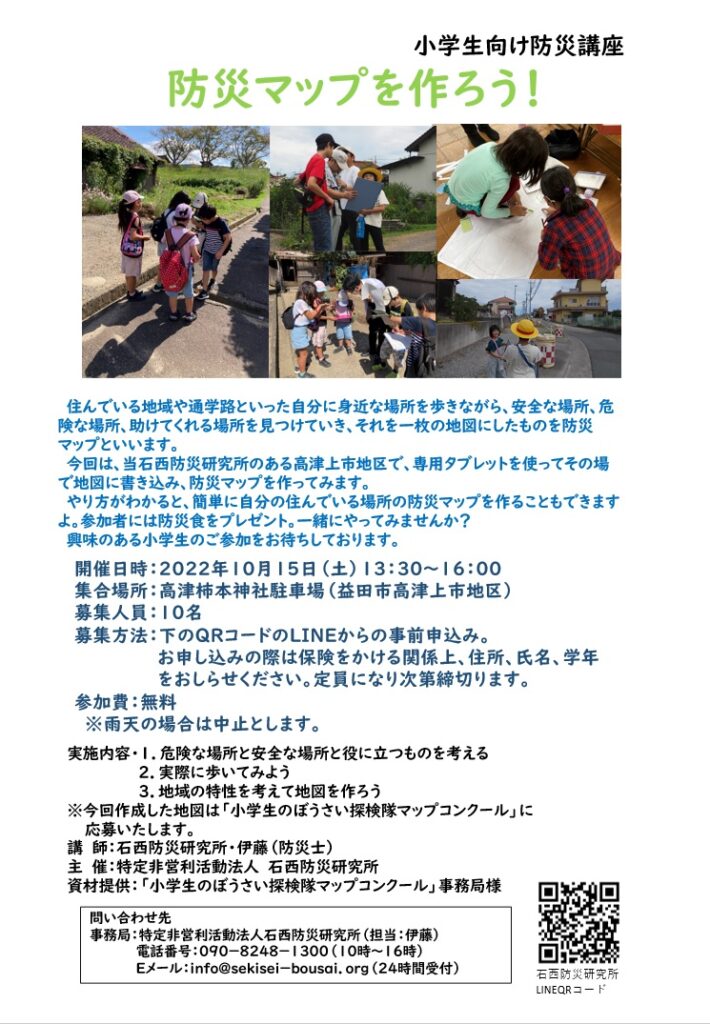あなたは津波などで避難が必要な状況になったとき、自分がどこへ避難すればいいのかを知っていますか。
また、ご家族がどこへ避難するのかを知っていますか。
学校や施設などにいるとき、そこからどこへ避難しているのかについては、案外と知られていないことが多いですので、どこに避難するのかをしっかりと確認しておきましょう。
できれば避難経路もあわせて確認しておくといいと思います。
どのような判断でどこへどんな経路で避難しているのかを知っていると、いざというときにもある程度どこにいるのかが予測がつきます。
そして、探しに行ったり迎えに行ったりするときにも迷わなくて済みます。
また、自分の子供が遊んでいるときに避難すべき状況が起きた時にはどこへ避難すれば安全なのかを、子供と一緒に現地で確認しておくと安心です。
誰がどこにいてどうなっているのかがわからないことは、人の心に不安を招きます。
その結果、その不安を解消するために助けに出かけて遭難するというケースは過去の災害でもたくさん起きています。
いざというときに誰はどこに避難しているのかを事前に知っていることで、そういった不安を排除することができますから、お互いにどのような行動をするのかについて、しっかりと話をしておくようにしてください。