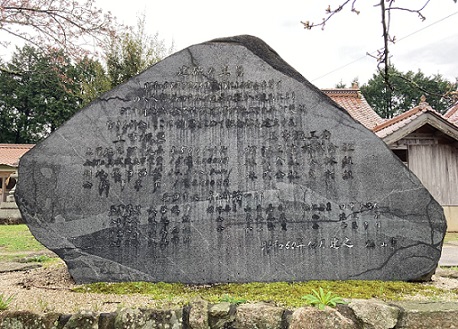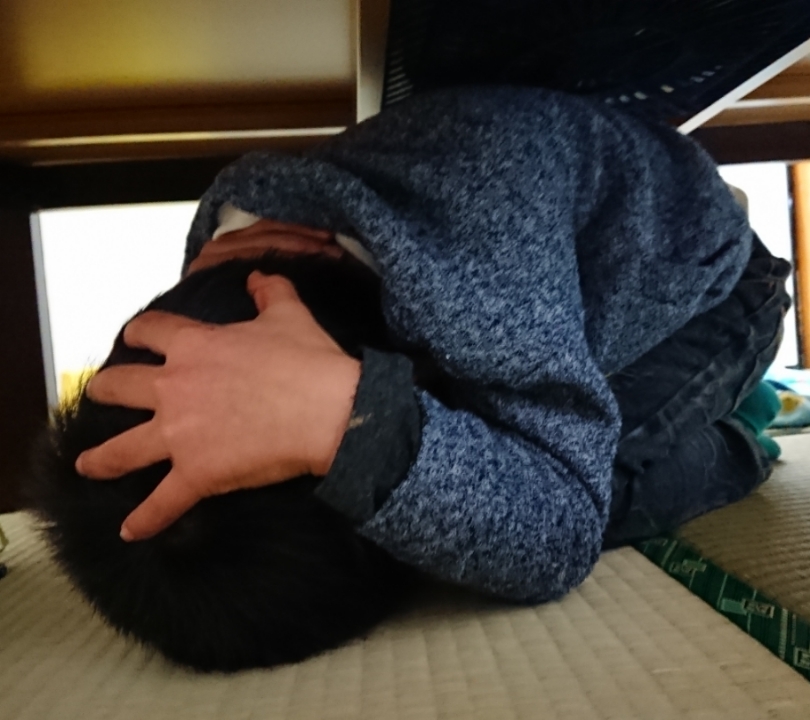最近あちこちで地震や水害など大きな災害が起きていますが、そのたびに問題になっているのが自分の生活を再建するための費用です。
しっかりとした貯蓄があればともかく、そうでない場合には、ある程度保険によってカバーする方法を考えてもいいと思います。
特に大きな金額になる自宅などの建物と、生活に必要な各種家財はそれなりの備えをしておいたほうがよいのではないでしょうか。
自治体からの見舞金や再建費用でなんとかなると考えている人も多いと思いますが、実際には生活再建さえままならない状態になっているのが現状です。
今回は災害と保険について考えてみたいと思います。
1.自治体等からの見舞金
災害時に自治体からの見舞金が出ることがありますが、建物が「全壊」「半壊」に対して出るのが基本となっていて、その判定は被災度判定調査によって決定されます。
あくまでも建物の状態によって支払われるものであり、その人の事情や状況は考慮されないことに注意してください。
他にも生活再建支援金などが出るケースもありますが、少なくとも建物や生活の再建に充分な金額ではありません。
ここではあくまでも自助が要求される部分であることを知っておいてください。
2.対応する保険
建物や家財は、損害保険が保険の引受先になります。
損害保険は、加入する保険会社や保険の種類、お住まいの地域などの条件によってさまざまですが、大きく分けると今現在の価値の金額を補償する「現存価格補償」と、被災した建物や家財を再調達するための費用を補償する「再調達価格補償」があります。
当然、条件がよい保険ほど掛け金も上がりますので、あなたの状況やあなた自身の生活再建計画に基づいて無理のない金額で保険をかけるようにしてください。
また、災害で受けられる建物や家財に対する損害保険は発生する災害によって異なりますので注意が必要です。
基本的には「火災保険」がベースになり、これに水害対応をつけると住宅総合保険となります。
地震保険は火災保険が契約されていないと契約をすることができないので、火災保険のオプションのような性格を持っています。
地震保険では、地震によって発生した火災、家屋倒壊または家屋埋没、噴火による家屋損壊、津波による家屋流出が補償されることになっています。
ここで気をつけないといけないのは、火災保険単独では地震による火災での焼失は補償されません。あくまでも火災のみが対象になっていて、原因が災害によるものは水害や地震といった災害特約が必要となることを知っておいてください。
3.もし被災したら
生活再建にはすぐにでもお金が必要となりますが、基本的には保険会社の調査員が現地を確認し、その損害状況を判定した上で支払うべき保険金を算定することになります。
ただ、大規模な災害だったり、すぐに解体しないと危険な場合などには調査員の調査が間に合わない場合があります。そのため、保険会社に連絡して承諾を得ることができれば、写真を撮って現地調査に変えることができることがあります。
自治体の被災度判定などにも使えますので、被災した場合には被災した家屋や家財など被災したものをあらゆる角度から撮影しておくことをお勧めします。
また、保険金の算出後はかなり早く支給がされるようですが、これも保険会社によって異なりますので、被災した場合には保険会社に相談することをお勧めします。
4.災害に備えて
火災保険や地震保険をかけていても、被災した後で速やかな手続きをとるためには保険をかけている保険会社や保険の証券番号があった方がよいです。
ですから、あなたのパーソナルカードの中にそれらの情報を追加しておいてもいいかもしれません。
また、大規模災害などでは損害保険協会に照会するとあなた自身がかけている保険会社や保険の証券番号を調べてもらうこともできますので、提供される情報に注意をしておいてください。
5.請求はご自身で
被災地で見舞金や保険金の話をする頃合いになると、あなたに代わって交渉しますという団体や個人が言葉巧みにあなたに迫ってきます。
でも、実際のところそういった団体や個人に頼んでも、あなた自身が手続きをしても、支払われる額は変わりませんし支払われるまでの期間も変わりません。
法外な手数料や手間賃を取られるのは無駄ですし馬鹿馬鹿しいですので、手続きはあくまでもご自身で行うようにしてください。
やり方が分からない場合でも、行政機関窓口や保険会社、その代理店であれば手数料なしで手続きの相談に乗ってくれます。
そんなに難しくありませんので、おかしなところに頼まずに、あなた自身で手続きをするようにしてください。
なお、今回記載した損害保険についてもう少し詳しいことが知りたい方は、日本損害保険協会のウェブサイトをご一読ください。
「損害保険とは?」(一般社団法人日本損害保険協会のウェブサイトへ移動します)