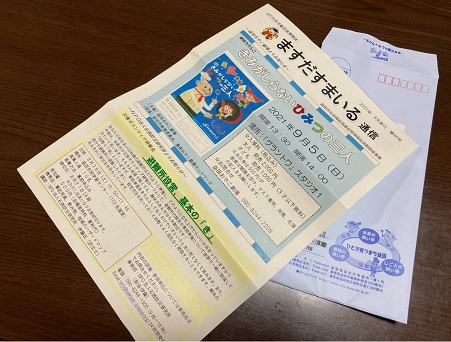前線停滞により、特定地域に雨が降り続いていて被害が大きくなってきそうな気配ですが、あなたのお住まいの地域ではどのようになっているでしょうか。気になるようでしたら、気象庁のウェブサイトのキキクルを確認してみて欲しいと思います。
■キキクル(気象庁のウェブサイトへ移動します)
当研究所のある島根県のお隣の広島県では大雨特別警報が発令され、最大級の警戒をするように呼びかけられています。
ところで、この特別警報はどういった意味を持っているのでしょうか。
警報と何が違うのか。
今日は気象庁のウェブサイトの記載を元に特別警報と警報の違いを確認しておきたいと思います。
1.「警報」とは
その地域で重大な災害の起こる恐れのあることを警告するための予報で、各地方気象台がもっている基準を元に発表されるものです。
そのため、地域によって警報の基準が異なっています。
暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮や波浪、浸水、洪水などの種類があります。
2.「特別警報」とは
特別警報とは、その地域の警報の発表基準を遙かに超える大雨や大津波などが予測され、重大な災害が起こる恐れが著しく高まっている場合に発表し、最大級の警戒を呼びかけるものです。
基準はその地域で数十年に一度起きるかどうかというもので、例えば東日本大震災の大津波や伊勢湾台風の高潮、最近では令和元年に東日本の広範囲で被害を出した台風の大雨などがそれに当たるそうです。
滅多に起きないがとても危険な状態であることを教えてくれるものと考えればいいと思います。
大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪が想定されていて、その中で「大雨特別警報(浸水害)」や「大雨特別警報(土砂災害)」といった風に細分化されています。
個人的には、警報は「災害が起きる可能性がある」、特別警報は「災害が起きる可能性が高い」といったイメージでいればいいのかなと思っています。
それにしても、「特別警報」は平成25年に設定され、50年に1回程度起きる規模の異常気象とされているのですが、ここ最近は結構頻繁に耳にするような気がしています。
原因はいろいろと考えられると思いますが、今までとは違う環境になってきているのかなと考えて、準備だけは怠らないようにしておきたいですね。