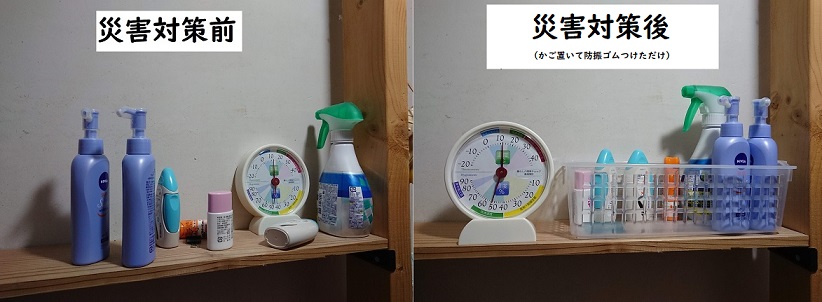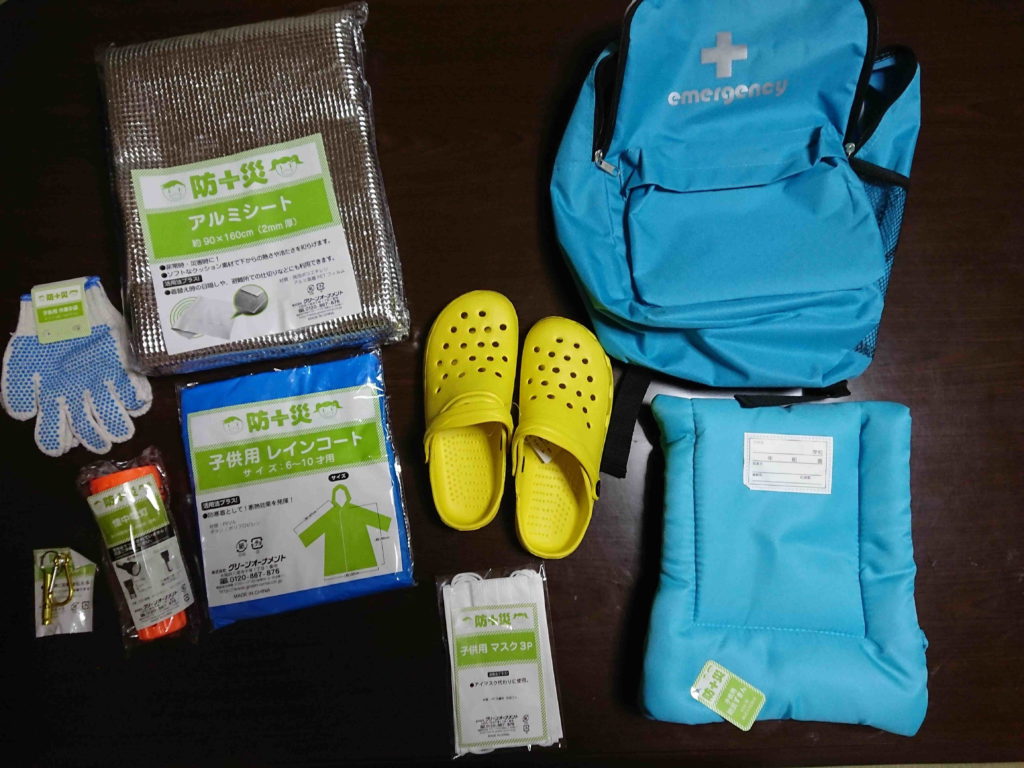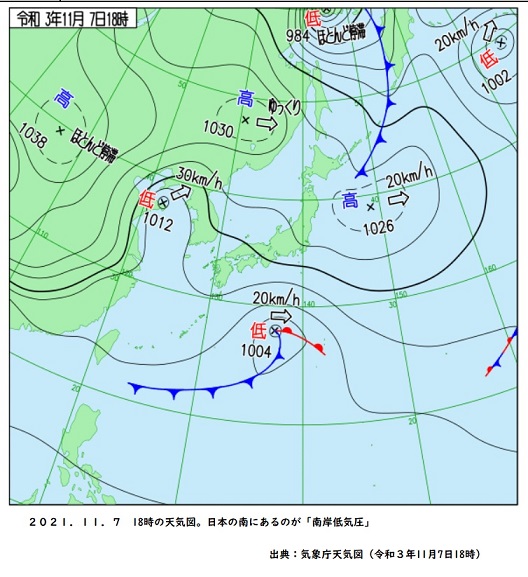救急ポーチの一例。消毒用として衛生綿が準備されている。
救急ポーチの一例。消毒用として衛生綿が準備されている。
あなたの非常用持ち出し袋には救急セットは入っていますか。
非常用持ち出し袋の作り方では、「救急セット」や「救急箱」と書かれてはいるのですが、その中身について具体的に触れているものというのはあまり見たことがない気がします。
今回はこの救急セットには何を入れておくといいのかを考えてみたいと思います。
1.持病の薬がいるならまずはそれから準備する
まず最初に準備すべきは、常に必要な薬があるかどうかです。
日常的に薬を飲まないといけない人は、まずはその薬を救急セットに入れてください。
目安としては1週間分です。処方せんが必要な薬の場合には、かかりつけのお医者さんに事情を説明して非常用として準備しておくようにしましょう。
処方せんが必要な薬にも有効期限が存在していますので、新しいものを受け取ったら、その都度救急セットに備えているものと入れ替えるようにしてください。
2.外傷に備える
絆創膏はちょっとした怪我や傷に使えて手間のいらない便利なものです。
いくつかの大きさを揃えておくと、ちょっとした怪我なら簡単に処置ができて助かります。
最近ではハイドロコロイドタイプの絆創膏も出ていて、これを使うと、貼り替えの手間が内上に傷跡が殆ど分からないくらいにきれいに直ります。
ただし、ハイドロコロイドタイプは傷口を密閉して身体の修復機能を利用するという構造上、傷口がきれいになっていないとかえって怪我を悪化させることも可能性としてありますので、傷口が充分に洗浄できない場合には通常タイプの絆創膏を使った方が安全かもしれないと思います。
次に滅菌ガーゼ。大きな擦り傷や抜くと命に危険がありそうな傷口の保護に使います。また、圧迫止血法を使うときには現金ガーゼを使うのが基本となりますので、いくつか準備しておきましょう。
器具としては、手当に使うはさみやピンセット、毛抜きといった道具類はセットのものも売っていますが、値段と性能がほぼ比例するものです。
そのため、入手できるのであれば個別に揃えた方が安くて良いものが揃うのではないかと思います。
滅菌、減菌されている必要はありませんが、救急セットに入れるのであれば、それなりに衛生的なものを入れてください。
そして粘着包帯。当然包帯として使えますが、それ以外にも添え木の固定具やテーピング、ちょっとしたものを縛るときなどにかなり役立ちますので、1セットはあったほうがいいと思います。
粘着包帯と滅菌ガーゼの組み合わせだと圧迫止血もしやすくなりますので、滅菌ガーゼとセットで考えるといいのではないでしょうか。
最後に使い捨てカイロと急速冷却剤。季節によって変わるかもしれませんが、小型の使い捨てカイロと急速冷却剤を入れておくといざというときに非常に役立ちます。
使い捨てカイロは体温の保全に、急速冷却剤は打ち身やねんざ部分を冷やすのに使えます。いずれも緊急用ですので、小型のもので充分だと思います。
基本となるのは以上の2つ。これなら準備することはあまり難しくないと思いますが、理由を説明しておきます。
持病の薬というのは、実はかなり準備優先度の高いものになります。携帯トイレ、水の次くらいに重要なのでは無いかと筆者は考えています。
せっかく命が助かったのに、持病の悪化で体調不良や亡くなってしまうようではなんにもなりませんので、非常用持ち出し袋だけでなく、普段持って歩く防災ポーチにも持病の薬は必ず入れておくようにしましょう。
それから、怪我に使えるアイテム類は自分で持っておかないとなんとかできるものではありません。そこで、怪我に対しては応急処置できるようなアイテムを揃えておくのと同時に、それらの道具類が使えるようになっておきましょう。怪我をしてから治療の手引き書を読むようでは、助かるものも助からないと思います。
・・・ひょっとすると、「こんなものでいいの?」と思われるかもしれませんが、こんなもので充分です。
後の準備については、おうちの救急箱を考えてみてください。普段どのような道具や薬を使っているでしょうか。救急箱に入っている薬や道具は、使うものと使わないものがはっきりとわかれていると思います。その中でよく動いていて無いと困るものを追加していけばいいのです。もし救急箱が無い、あるいは中身が動いていないおうちの場合には、追加アイテムも不要だと思います。
最後に、これらを救急ポーチに入れるときには、それぞれのアイテムをチャック付きビニール袋にいれて収めるようにします。
これは避難時に非常用持ち出し袋がずぶ濡れになったとしても、持病や応急処置に使うものは濡らさないようにするためです。
蓋を開けるととても簡単な救急ポーチですが、例えば新型コロナウイルス感染症対策だとここにマスクや非接触型体温計などが必要になるかもしれません。それらのことも踏まえた上で、あなたにベストな救急ポーチを作ってもらいたいなと思います。