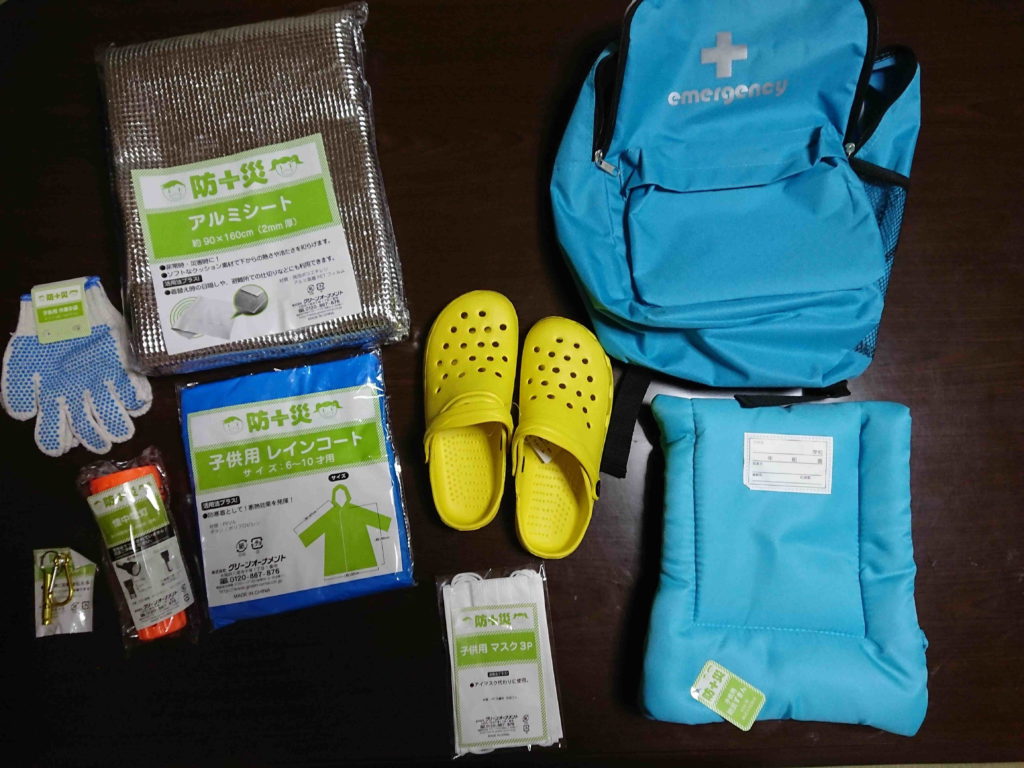大災害が起きると、発生後すぐに金品や物品の寄附をしようとする人がいますが、その行為、少しだけ待って下さい。
現地の状態がわからないのに金品の寄附の受付を始めるところは、本当にその寄付金が現地に届くかどうか、しっかりと調べることが必要です。
いろいろと言われていますが、日本赤十字社は赤十字社という全世界に繋がるネットワークがありますし、会計報告もきちんとされています。
もしも寄附をするのであれば、ここを基準にしてどのような寄附の使い道があってどれくらい明朗会計なのかを確認しても遅くはありません。
どのみち寄附したお金がすぐに現地に届くわけではないですから、一呼吸おいて、状況がはっきりしてからの寄附でも充分間に合います。
せっかくの善意を、悪意ある人に利用されないようにしてください。
それから、物品の寄附もできれば止めてください。
物品の寄附をしてもよい人は、現地に直接持ち込めて受取人が明確である場合だけです。ただ、災害発生後すぐに物資を持ち込もうとするのは、現地への災害救助派遣や救助活動の邪魔になりかねませんので、持ち込むのであれば他の活動の邪魔にならないようにご配慮願います。
そして、物品を送る人が忘れがちですが、災害が発生してダメージを受けているのは物流も一緒です。善意でものを送りつけようとすると、ダメージを受けている物流にさらなる負荷をかけてしまって、結局届いた頃には必要ない状態になっていたりすることが殆どです。
ちなみに、災害後の個人からの任意の救援物資でかなり困るものが、生鮮食料品と古着です。物流がダメージを受けている以上、平時と同じように物品が届くなどと考えないで下さい。流通の回復には時間がかかりますので、生鮮食料品を送っても、100%腐ってゴミになってしまいます。
また、不要な古着を送るのも絶対に駄目。あなたが着ないものは他の人も着ません。送るのならば新品のものを、できるだけ箱単位で送って下さい。
送りつけられた古着は、ほぼ100%現地で焼却処分となっていて、そうでなくても負荷のかかっている現地のゴミ処理にさらなる負荷をかけてしまいます。
マスコミの報道やSNSなどで「○○が足りない!」と発信されることはよくありますが、その後その○○が山のように届いて処分に困る状況になることはよくあります。
物資の調達は現地からでもできますから、慌てず騒がず、せっかくの善意を無駄にすることの無い方法で届けてください。
最近ではAmazonやヤフー、楽天などで現地の必要としているものと提供する人のマッチングサイトも災害時には運営されるようになってきています。
そういったところを利用して、いるものをいるぶんだけ必要な場所に届くようにしたいですね。
せっかくの善意が現地にとって悪意にならないように、金品や物品を送るときには、しっかりと配慮して欲しいなと思います。
参考:支援物資等を提供する(NPO法人レスキューストックヤードのウェブサイトへ移動します)