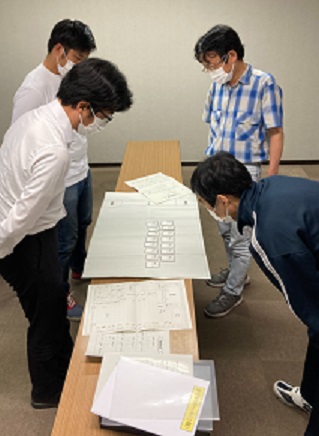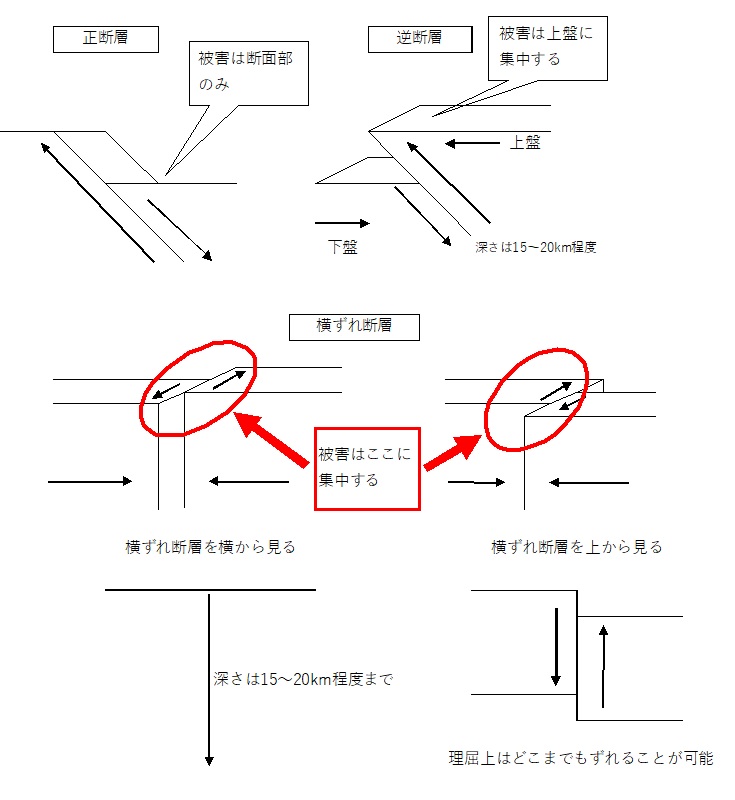地震が続いていますが、あなたのおうちの家具の地震対策はできていますか。
地震対策には二つあって、ひとつが家具そのものが倒れないようにすること、そしてもう一つが、家具の中身が落ちないようにすることです。
家具そのものが倒れないようにするには、転倒防止用の固定器具を使うのが一般的で、例えば突っ張り棒や転倒防止用の固定器具、家具を壁にビスで固定するなどの方法があります。
家具の中身が落ちないようにするためには、家具への中身の詰め方の工夫や、扉をロックするといった方法があります。
でも、例えば借家などで簡単に家具の固定が壁にできなかったりする場合があると思います。
もっとも簡単な家具の転倒防止は、家具の正面下、床と家具との間に折りたたんだ新聞紙などを入れて、家具を壁側に少しだけ傾斜させる方法です。

我が家では昔からばあちゃんが普通にやっていて、何も考えずに筆者自身もやっていたのですが、これをやると家具が簡単には転倒しなくなります。
直下型地震のような大きな縦揺れを受けるとどうにもなりませんが、普通の地震の揺れなら、家具の上側が壁で支えられているために転倒することがなく、引き出しや扉が若干上を向いていることから、簡単には抜けたり開いたりしません。
簡単にできて非常に効果的な地震対策ですので、もしもお引っ越しなどで家具を動かすことがあるのであれば、家具の下に折りたたんだ新聞紙を入れるとよいと思います。
ちなみに、同じような機能を持った道具が百円均一ショップやホームセンターなどで売られているので、見た目を気にする方はそちらで調達してもいいと思います。
地震が起きたときに怖いものの一つが家具の転倒です。
ちょっとした工夫で転倒が避けられるのであれば、やっておいて損はないのではないでしょうか。