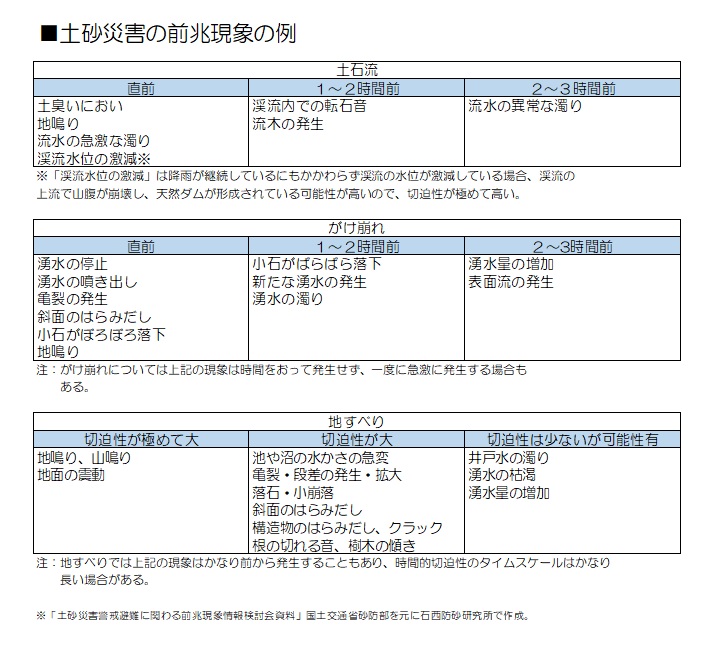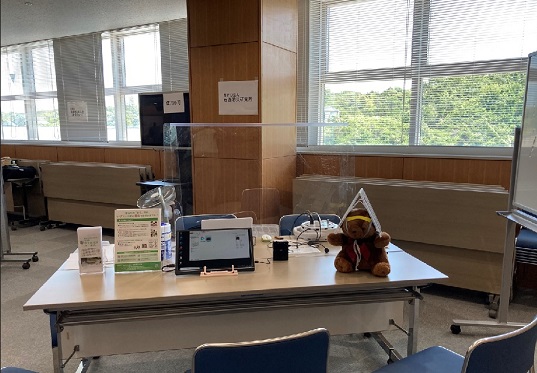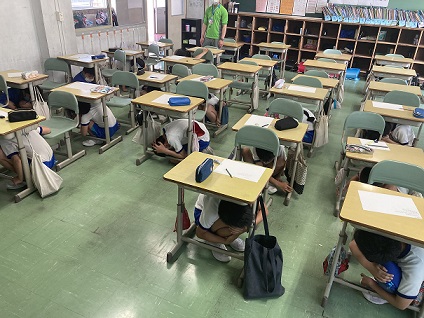先日海辺で外あそびごはんの会を開催しましたが、そのときの大きなテーマの一つが「海水から塩を作る」というものでした。
人の生活に欠かせない塩を作るのにはさまざまな方法がありますが、どれもかなり大規模で簡単に塩が作れるような感じがしません。
でも、海水自体は「塩が溶けている水」なわけですから、火に掛けて水を蒸発させてやれば塩は作れるはず。
というわけで、当日参加してくれた子ども達と一緒に塩を作ってみる事にしました。
 ひしゃくで上澄みを掬うと砂が入りにくい
ひしゃくで上澄みを掬うと砂が入りにくい
まず最初に、生活排水の入りにくい海岸で海水を汲んできます。
 鉄鍋一杯の海水で塩を作ってみます
鉄鍋一杯の海水で塩を作ってみます
それを、鉄鍋に入れて、その鉄鍋を火に掛けます。
 天気がよかったので、火のそばはとても暑かったです。人肌に塩ができるくらいでした。
天気がよかったので、火のそばはとても暑かったです。人肌に塩ができるくらいでした。
ひたすら火に掛けていると、1時間半を過ぎた頃、一気に沸騰しました。
 飽和状態を超えると、一気に水分の蒸発が始まるようです。
飽和状態を超えると、一気に水分の蒸発が始まるようです。
それが治まると、鍋の底には白っぽいものが残りました。
 水分が全部飛んだ状態。きのこみたいにも見える。
水分が全部飛んだ状態。きのこみたいにも見える。
削ってみると、塩っぽいです。
 箸でつつくとホロホロと崩れて粒子になりました。塩です。
箸でつつくとホロホロと崩れて粒子になりました。塩です。
食べてみたら、塩辛いのですが、後味すっきりのおいしい塩ができました。
当日はお昼ごはんに火を焚いていたかまどの中でズッキーニを焼いていたので、それにつけてみたり、農家さんからいただいた野菜と切り干し大根で作った野菜スープに加えて味の変化を楽しんだりしていました。
しまいには、塩だけなめている子も出てきて、今回は大成功だったかなと思います。
ただ、小さな袋1つの塩を作るのに1時間半以上煮詰めていくのは、根気と燃料がかなり必要です。
塩田式や流下式など、ちょっと手間はかかりますが、燃料代がかからない作り方が普及した理由がよくわかりました。
思ったよりも簡単にできますので、今年の海あそびで試してみるのも面白いかもしれませんよ。
ちなみに、もしやってみるのであれば、鍋はアルミ製以外のものを使うようにしてください。アルミだと、塩を作る過程で鍋がかなり傷んでしまいますので。