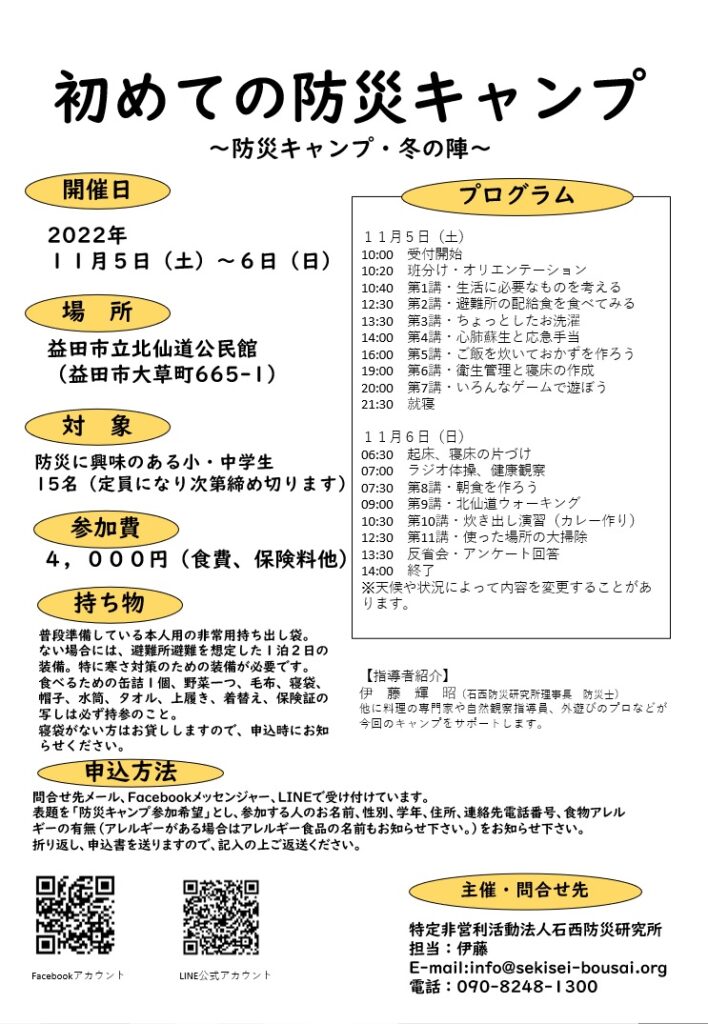人間の三大欲求として「食欲」「性欲」「睡眠欲」があるそうですが、排せつしたいという要求はひょっとしたら、この三大欲求よりも強いのではないかと思うことがあります。
排せつしないという選択肢は存在しないので、トイレは絶対に必要なのですが、実はあまり重要視されていないのかなと思うことがあります。
最近でこそトイレトレーラーの配備が自治体で始まっていますが、自治体はまだまだトイレ問題には取り組む気がないように見受けられます。
でも、トイレは我慢できません。というよりも、トイレは絶対に我慢してはいけません。
体から不要なものを外に出す作業が排せつですので、これを我慢すると体調不良を簡単に引き起こします。
また、避難所など人がたくさんいる場所でその辺にしようものなら、汚物と臭いで大惨事になることは間違いありません。
災害が起きてから仮設トイレが来るまでの間、トイレをどうするかという問題は真剣に考えておく必要があることだと思います。
最近は携帯トイレや簡易トイレにもさまざまなものがありますが、自分が使いやすいものを用意しておきましょう。
そして、できれば便座を使わなくても済むタイプの簡易トイレを準備しておくといいと思います。
というのも、トイレの便座を利用した簡易トイレはたくさん出ていますが、トイレが被災しないとは言えないからです。
トイレが被災すると便座が使えませんから、せっかく準備した簡易トイレが使えないという事態になります。
それに備えて、座る場所付きの簡易トイレを準備しておいてほしいのです。
もちろん避難所にそういった準備があるなら、便座を使うタイプの簡易トイレで問題ありませんので安心して使うこともできると思います。
災害時にはさまざまな問題が起きますが、自分が無事だった場合に最初に直面するのがこのトイレの問題です。
水や食料だけでなく、携帯トイレや簡易トイレについても、3日~1週間程度の準備をしておいて、できるだけトイレの質も落とさないようにしたい