各自治体が耐震補強に対する補助を行っているようですが、なかなか耐震補強が進んでいない現実があります。
一般住宅に限らず、会社や古いビルなどでも耐震化が進んでいないのですが、予算がないからといって後回しにしていい問題ではないことに気づいている方がどれくらいいるのかなと考えます。
震度6強以上の地震に遭った場合、古い家や会社、ビルなどは倒壊する危険性があります。
石西地方でもいつ揺れてもおかしくないと言われている弥栄断層が存在していますが、これが動くと最大でマグニチュード7.7程度の地震が起きる(政府地震調査研究推進本部)と予測されています。
情報が少ないためにいつ頃動くかは不明ですが、いつ動いても不思議ではないということでもあるので、今この瞬間にも揺れるかもしれません。
でも、もし地震が発生したら、その時になって慌てて地震対策をしようとしても手遅れです。地震で生き残るためには、とにかくものの下敷きにならないことですが、古い家屋に人がいて倒壊した場合、かなりの確率で圧死することになってしまます。これは運が悪かったでは済みません。耐震補強しておけば助かったわけですから、想定外では無く人災になるわけです。
特に会社やビルなどで倒壊が起きたとしたら、耐震補強にかかる経費以上にさまざまな出費を強いられた上に信用まで無くなるという、ある意味では致命的なダメージを負いかねない状況になります。幸い建物全てを耐震補強しなくても一部を補強したり一室だけを補強するなど、最近ではいろいろな方法がありますので、いくらかお金をかければ対策は充分に取ることが可能な時代になっています。
地震の怖いところはいつ来るか分からないところですが、地震は地面が揺れるだけですから、対策さえきちんとできていれば死ぬ可能性を下げることができます。
繰り返しになりますが、地震で倒壊した家屋の下敷きになって圧死することは想定外ということができません。
耐震補強は高く感じるかもしれませんが、あなたや従業員、関係する人のの命の値段と考えてみたら、それでも高いと感じますか。
かけた費用の分だけは確実に安全が確保できる。そういう意味では、地震は相手にしやすい災害なのかもしれませんね。
カテゴリー: 基本的なこと
ハザードマップの検証をしていますか
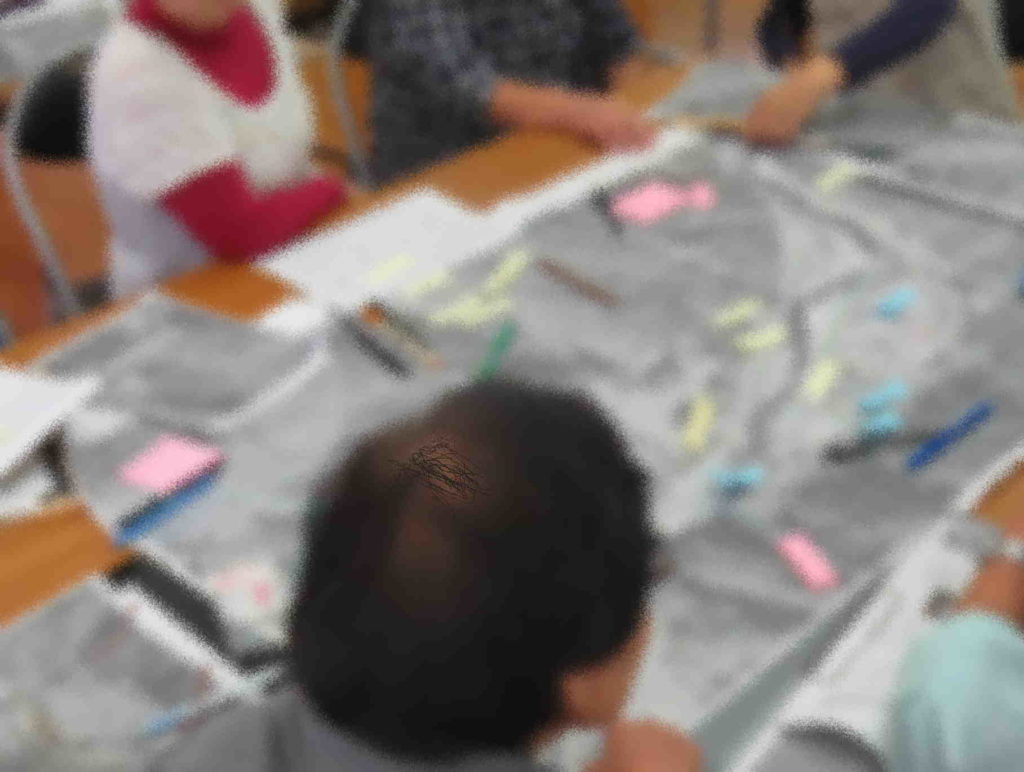
各自治体ではハザードマップを作成して自治体内の世帯に配布していますが、あなたは見たことがありますか。
ハザードマップは特定の条件下での被災状況を図化したもので、自治体や地域の避難計画作成の基礎となる資料の一つです。
これには地震や浸水害、土砂崩れの危険性が色分けで表示されていて、とりあえずの危険な場所がわかるようになっており、あなたが避難計画を作るときには必ずこれを見ているはずです。
ハザードマップの検証では、自宅からの避難だけでは不十分です。勤務先や通学先、途中の経路、よく買い物や遊びに行くところ、そして自分が避難すべき避難所の災害対応状況といったものも確認しておかなければいけません。
避難所は災害から身を守るために避難するところなので、避難すべき避難所がどのような災害に対応しているのかを正確に把握しておかなければ、避難した避難所で被災したと言うことになりまねません。
想定される災害のハザードマップに、地域の災害伝承の情報を追加すると、より安全な避難を行うことができるようになりますので、分かる範囲で確認して追加しておきましょう。
避難経路は状況や環境の変化によって常に見直しが必要ですし、地域としての防災マップ作りも必要となるでしょう。
今住んでいる場所だけでなく、自分が行きそうな場所の経路と安全性を確認しておいて、いざというときに備えたいですね。
パーソナルカードを作っていますか
自分の情報や家族を始めとする大切な連絡先、家族の写真などをまとめて一枚のカードにしたものをパーソナルカードと言いますが、あなたはパーソナルカードを持っていますか。
被災して動揺すると、知っているはずのことが思い出せなかったりすることがあります。そのとき、このパーソナルカードを確認することで非常時の連絡先や家族の集合場所、かかりつけ医などの情報を確認することができます。
また、子どもやお年寄りに持たせておけば、非常時にそれを確認することで安否確認などの連絡を取ったり身元の確認をすることができます。
こういった書式で作る、という指定されたものはありませんが、自分の名前、住所、血液型、家族構成、家族の連絡先、災害時の集合場所、持病や常備薬、かかりつけ医やかかりつけ薬局などの情報、そして家族写真を一緒にしておくと非常に役立ちます。
とはいえ、このパーソナルカードは個人情報の塊ですから、いざというとき以外人に見られたくない方もおられると思います。
そのため、作ったものをラミネートパウチしておいて、使うときにははさみで切って中を確認するといった方法をとることもあります。
大切なことは、非常時に自分が誰で家族が誰で、どこへ連絡すればいいのかなどがわかることですから、作ったものを普段持ち歩くカバンや財布にいれて、いざというときに使えるようにしておきたいですね。
万能な新聞紙
最近のご家庭で姿を見なくなってきたものの一つに新聞紙があります。
さまざまな理由から新聞を取らなくなっているおうちが増えているのですが、こと防災の視点で見ると、新聞紙というのは非常に役に経つ道具です。
床に数枚敷くととりあえず床からの寒さをシャットアウトできますし、服の中に着込めば暖を取ることもできます。もちろん焚き火の焚き付けや薪代わりに使うこともできますし、ちょっと工作すれば寝袋や食器、帽子や服まで作れます。
広げて紐からぶら下げれば居住スペースの仕切り代わりにも使えますし、汚物処理などにも大活躍。あって困るものではありません。
ただ、新聞紙を持っていても使い方がわからなければただの新聞紙にしかなりません。紙の特性を知って、いろいろなタイミングで試してみることで、自分に合った使い方や必要な枚数が分かってきますから、時間を作って一度工作してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、大きなビニール袋と新聞紙を組み合わせると、とても暖かい防寒着を作ることができます。
見た目は美しくないのですが、暖かくて湿気も溜まりにくいので、割と快適に過ごすことができますから、興味のある方は調べてみてくださいね。
【活動報告】第3回高津小学校防災クラブを開催しました
去る11月4日、益田市立高津小学校様で防災クラブの第3回目を開催しました。
今回は「止血法と搬送法その2」と「校内安全点検」、それに「ビニール袋工作」の3つから子ども達に選んでもらう形にしたのですが、見事に3つにわかれてしまい、結局代表者がじゃんけんして「止血法と搬送法その2」をやることになりました。
前回は直接圧迫止血法と前屈搬送法をやりましたが、今回は間接圧迫止血法といすを使った搬送法、そして実際にけが人の手当から搬送までを演習してみてもらいました。
間接圧迫止血法は止血帯を使った止血方法ですが、実際に子ども達がするの危険なので講師の腕に止血帯を巻き付け、止血帯を締める前と締めた後の手の温度を確認してもらい、締めた後手が冷えていくことを確認してもらって血流が止まっていることを知ってもらいました。

また、担架の搬送法ということで、階段での搬送を実際に担架を使ってやってみてもらい、二人では階段で水平が維持できなくなること、そして運び手の数が多いほど危険が少なくなることを実際に体験してもらいました。その後いすによる搬送をやってみて、担架での搬送がどれくらいやりやすいのかということを体験していました。
最後は担当の先生をけが人役に見立てて圧迫止血から担架搬送までを実際にやってみてもらいました。

先生の腕と足を怪我しているという想定で、実際に怪我している部分を圧迫止血し、血が止まったら包帯を巻いて固定してもらったのですが、なかなか思ったようにできずに苦戦していました。
搬送では、床から担架へ先生を移動させるのにいろいろと試行錯誤していましたが、なんとか無事に載せて搬送することができました。
実際にやってみると、なかなか思ったようにはできないということと、声をかけあわないと危険だということを理解してもらえたと思います。
子ども達はノリノリでやってくれているのですが、そのノリを生かせないことにもどかしさを感じ、講師としてはまだまだ未熟だなと反省しきりでした。
ともあれ、今回防災クラブでつきあってくださった先生と子ども達に感謝します。
火を起こせますか
災害後、どうかすると火を自分で作らなければいけない事態が起きることがあります。
昔はたばこを吸う人があちこちにいて、火をつけるためのライターやマッチを持っていたものですが、最近は電子たばこになったそうで、マッチやライターは使わなくなったと聞きます。
簡単に火をつける道具を持っていればいいのですが、そうでない場合には何とかして火をつける必要があるのですが、あなたは火をおこす方法をどれ位知っていますか?
火打ち石やファイアスターターに始まり、虫眼鏡やペットボトル、太陽光反射や摩擦による火起こしまで、火を作る方法はいろいろとあります。

ただ、その方法を知らなければ何の役にも立ちません。
最近は火は危ないと言うことで日常生活からどんどん遠ざけられていますが、危ないからといって知らなければ万が一の時には自分の命が危なくなります。
あなたが持っている非常用持ち出し袋や備蓄品のセットで火を作ることができますか。また、火を維持することができますか。装備の見直し時には、そういった点も考えながら準備してください。
72時間の意味
エーゲ海で大きな地震が起きました。マスコミでは地震発生から72時間を過ぎると建物などに閉じ込められた要救助者の生存が殆ど絶望のような報道もされていますが、なぜ72時間なのか考えたことがありますか。
今日はこの72時間という時間について考えてみたいと思います。
72時間以内にできるかぎりの救助をしなければ生存者が極端に減ってしまうと言われています。これは阪神淡路大震災で倒壊した建物などから救助できた生存者の割合が、初日は74.9%だったのが2日目には24.2%、3日目、すなわち72時間後には5.4%となり、72時間を過ぎるとかなり下がってしまうことが示されたためです。(出典:「阪神・淡路大震災の経験に学ぶ」 国土交通省近畿地方整備局作成)
もっとも検死報告書では死者の殆どは圧迫死による即死状態ともあるためこの数値をそのまま鵜呑みにすることもよくないようですが、被災後早ければ早いほど助かる人が増えるのは事実です。(出典:阪神・淡路大震災教訓情報資料集【02】人的被害 内閣府作成)
また、水は3日飲めないと脱水症状を起こして死に至るからだという話もあります。これも72時間以内の救助が言われている原因でしょうが、通俗的に言われているものなので何か確証があるようなものでもなさそうです。
最終的に生存できるかどうかは本人の体力や閉じ込められた環境、天候などにかなり左右されるので、72時間を超えたから生存者がいないというわけでもありません。
ただ、救命率を表す72時間という表現は要救助者がいる人にとっては一つの目安になる数値です。さまざまな要因でこの時間内に救助が間に合わない場合には、あきらめがつくという効果もあります。
マスコミは大規模震災が起きたときに批判的に使われることもありますが、これも数値があることで起きる一つの現象ではあります。
ちなみに、この数値は人命救助以外に備蓄品の目安や自助でなんとかすべき時間の目安にもなっているので、いろいろな意味で災害対策とは切り離せない数字なのだと思います。
消防の緊急消防援助隊や警察の広域緊急援助隊、自衛隊などの救助のプロ達は生存者がいると思われる場所で重点的に救助活動をします。
つまり、生存者がいないと判断されてしまえば、そこに救助隊が来るのは72時間よりもずっと後になってしまいますから、閉じ込められたときに備えてホイッスルを準備しておくことをお勧めします。
また、一番良いのはそもそも倒壊に巻き込まれたり閉じ込められたりしなくてもすむような環境を整えておくことです。おうちや周囲の地震対策をしっかりとやっておいてくださいね。
安全の優先順位
「安全は全てに優先する」というのが建設現場などで掲示されていることを見たことはありませんか。「セーフティーファースト」の日本語訳だそうですが、「安全第一」という方がわかりやすいかもしれません。
ただ、この安全に順位があるとしたら、あなたはどう考えますか。
災害対策では、この安全の定義がよく変わります。
発災直後では、安全とは「身体の安全」に他なりません。何を置いてもまずは逃げて自分の命を守ることが最優先される安全です。
発災後は、自分がこの先どうなっていくのかという不安を解消することが優先される安全になってきます。
そして、発災後しばらくすると、今度は収入や仕事、衣食住といった生活の安全が優先されています。
それぞれ全て安全には必要なものなのですが、時期と状況によって優先されるべき安全の順位が異なってくるということで、防災支援活動では時間の経過によって変わるこれらの優先順位にどう答えていくのかが大切になります。
被災後にすべてが元通りになることはありません。ですが、被災者の居心地のよい安全を確保するためにさまざまな支援を行っていく必要があるのです。
コロナ禍で起きた災害では、災害復旧を支援する人達はかなり限られた状態になりました。その結果、復旧が遅々として進まない状況の場所もあるようです。
そんな中でも、被災者の安全を確保するために、現地の支援者達は様々な知恵や工夫を凝らして活動をしています。
あなたに考えておいて欲しいのは、もしも自分が被災者になったとき、さまざまな安全をどうやって確保するのかということです。自分が対応策を準備しておけば、安全が安心に変わって激しく不安にならなくても済むからです。
そのために作るのがBCP(事業継続化計画。ご家庭の場合だとFCP(家族継続計画)ともいいます)で、実はこれが一番の災害対策といえるかもしれません。
安全の優先順位は変わっていきます。それに合わせた自分が生きるための継続化計画を、きちんと作っておきたいですね。
同行避難と同伴避難

ここ最近の避難せずに救助されることとなった人の理由の中にペットを置いていけなかったという事例が増えてきているそうです。
そのため、最近では原則としてペットと一緒に避難所へ避難せよという方向になっていて、環境省が「人とペットの災害対策ガイドライン」を出し、各方面に向けて飼い主・ペット一緒の避難について呼びかけを行っています。
ただ、避難所の受け入れ体制が必ずしも整っているわけではなく、ガイドラインでも同行避難と同伴避難というややこしい書き方がされているため、避難所でトラブルが起きる元となっています。
今回はこのペットの同行避難と同伴避難の違いについて考えてみます。
1.同行避難
同行避難とは、災害時に避難する飼い主とペットが一緒に避難することです。
ただ、避難した後の取り扱いが異なり、飼い主とペットが一緒に過ごせる場合、ペットが別の空間に分けられる場合があります。
収容能力が低い避難所では、避難してきたペットは野ざらしか特定の屋外のスペースにいろいろな動物が一緒くたにされてしまうこともあり、ペットのえさや排泄処理などは自己責任の範疇です。
ケージなどの狭い空間に押し込められることになるので環境も悪く、せっかく避難したけれど見るに見かねて元の家に戻ってしまうような飼い主・ペットもいます。
2.同伴避難
同伴避難は、災害時に避難する飼い主とペットが一緒に避難し、避難所で一緒に生活することができる状態です。
飼い主とペットにとっては一番の理想型ですが、家庭毎に部屋が割り当てられることは殆ど無く、動物の種類毎に部屋が割り当てられる状態なので、しつけがきちんとできていないと他の人のペットとの諍いが発生したりします。
実際のところ、同行避難と同伴避難の境界はかなり曖昧なので、避難してみたら同行避難が同伴避難になったり、その逆も起きたりします。
もともと人の避難所の数が足りていないという現実があり、一緒に避難してもペットが苦手な人やアレルギーを持っている人、糞尿や鳴き声の問題などいろいろと解決しなければいけない問題が多いですから、あらかじめペットの扱いについてきちんと避難所で取り決めておかないと発災後すぐに大きな問題となってきます。
ちなみに、聞いた話ですがペット対策を考えているある地域ではペットお断りの避難所とペットと一緒の避難所に、避難所を物理的に分けて運用しているところがあるそうです。そういうのも一つの解決方法かもしれません。
ともあれ、同行避難にしても同伴避難にしてもペットに対しては飼い主が全ての責任を負うことになります。ケージの準備、えさや水、糞尿の始末、しつけ、予防接種などの前提条件がありますから、問題がないように飼い主の責任はきちんと果たしておかないと自分が困ることになります。
また、ペットを連れての避難は、自分の非常用持ち出し袋だけでなく、ペット用の非常用持ち出し袋も持って行かなければなりません。
そう考えると、ペットと一緒に避難をしたいと考えている人は普通の人よりも早めに避難行動を開始した方がよいかもしれません。
また、ペットと一緒に避難する人は普段から地域の防災情報をしっかりと知り、地域防災計画にもペットの問題を提起してしっかりと関与しておく方が安心です。
まだまだ始まったばかりのペットと一緒の避難行動。犬や猫だけでなく、さまざまな動物がペットとして飼われています。
それらへの対策をどのようにしていくのか。普段から地域でしっかりと話をしておきたいですね。
非常用持ち出し袋あれこれ

地震や大雨、津波などで避難しなければいけないとき、自分の命を繋いでくれるのが非常用持ち出し袋です。
仕事や学校等で家にいないことも多いかもしれませんが、できれば普段自分が居るところには何らかの形で置いておくといいと思います。
持って歩けるのであればそれが一番いいのですが、普段使いするにはなかなかかさばるものですのでそのあたりはあなたの都合に合わせて準備しておけばいいと思います。
ところで、この非常用持ち出し袋への詰め方について考えたことがありますか?
普段から山歩きやハイキングなどでリュックサックを使っている人には割と常識なのですが、底には軽いもの、上には重たいものを入れます。
重心が体に近く上にある方が重さを感じにくいので、できれば背中側が重たくなるようにしておくと非常に背負いやすいと思います。
中に非常用持ち出し品を収めるときには、濡れては困るもの、特に下着や着替え、タオルなどはビニール袋に入れておきます。完全防水のリュックサックならともかく、普通のリュックサックでは防水仕様でも長時間水にさらされるとファスナーから水が少しずつ染みこんできますので、安心せずにしっかりとした対策をしておくことです。
ビニール袋は、できればかさかさと音のしないものを選んでください。避難所でのかさかさ音は、気にする人にはものすごく気になる音のようで、このかさかさ音がトラブルになることもあります。
非常用持ち出し品についてはいろいろなところでいろいろなものが書かれていますので、あなたの都合と袋の容量を考えながら用意していただければと思います。
もしも準備するときに悩んだら、優先順位は排泄、給水、体の乾燥の順番で準備をしてください。食事は、無理に非常食では無く、自分が楽しんで食べられるものを準備しておいた方がいいです。
その上で余裕があればカセットコンロや石けん、無水シャンプーなどの衛生用品、バケツ、ラジオなどを入れていくといいでしょう。
普段の生活を考えて、なるべく質を落とさなくて済むようなアイテムを揃えておくといいでしょう。
最後に、非常用持ち出し袋には非常時に使うものを詰めておくわけですが、アイテム類の使い方をしっかりと覚えておいてください。
どんな便利なアイテムであっても、使えなければないのと一緒です。
アイテムは使いこなしてこそその存在が重要視されるということを忘れないようにしてください。
